終活、何から始める?その悩みを解決します
「終活」という言葉は知っているけれど、「具体的に何から手をつければいいのか分からない」「自分にはまだ早いのでは?」と感じている方は少なくありません。しかし、終活は単なる“死への準備”ではなく、これからの人生をより自分らしく、安心して生きるための前向きな活動です。
この記事では、数ある終活の項目の中から、専門家の視点と各種調査データを基に「本当に重要なこと」をランキング形式でご紹介します。この記事を読めば、あなたが今すぐ取り組むべきこと、そしてその具体的な進め方が明確になります。
そもそも終活とは? なぜ今、重要性が高まっているのか
終活とは、「人生の終わりのための活動」の略で、自らの人生の最期に向けて、医療や介護、財産、葬儀などについての希望をまとめ、準備することを指します。かつては家族や地域社会が担っていた役割を、個人が主体的に行うようになったのが現代の終活です。
その背景には、少子高齢化や核家族化の進行があります。オリックス銀行のコラムによると、頼れる家族が少なくなった現代では、老後や死後に備える必要性が高まっています。また、価値観の多様化により、「自分らしい最期を迎えたい」と考える人が増えたことも、終活が注目される大きな理由です。
終活の3大メリット
- 家族の負担を軽減できる:万が一の時、残された家族が手続きや判断に迷うことが減ります。
- 相続トラブルを回避できる:財産の分け方を明確にすることで、家族間の争いを未然に防ぎます。
- 残りの人生を前向きに生きられる:人生を振り返り、やりたいことを明確にすることで、毎日をより豊かに過ごせます。
【専門家が解説】終活で整理すべき項目・重要度ランキングTOP10
終活でやるべきことは多岐にわたりますが、すべてを一度に行うのは困難です。そこで、遺された家族への影響度、法的な重要性、そして緊急性の観点から、取り組むべき項目の重要度をランキングにしました。このランキングは、ベストファームグループの調査やハルメク 生きかた上手研究所の調査など、複数の意識調査で「重要」または「関心が高い」とされた項目を基に、専門家の視点を加えて作成しています。
- 財産整理と相続対策
- 医療・介護の意思決定
- 身辺整理(モノ・デジタル)
- エンディングノートの作成
- 葬儀・お墓の準備
- 連絡先リストの作成
- 保険・年金の見直し
- 自分史の作成
- ペットの信託・引継ぎ
- 専門家への相談
次章から、各項目について詳しく解説していきます。
【ランキング1位~3位】最優先で取り組むべき3つのこと
まずは、法的・金銭的な影響が大きく、家族の負担に直結するTOP3から見ていきましょう。これらは健康で判断力があるうちに、最優先で手をつけるべき項目です。
1位:財産整理と相続対策|家族の負担とトラブルを未然に防ぐ
終活において最も重要なのが、お金に関わる準備です。相続トラブルは資産家の話だと思われがちですが、司法統計によると、遺産分割で揉める家庭の約77%は遺産総額5000万円以下の「ごく普通の家庭」です。トラブルを避けるため、そして家族が手続きで困らないために、以下の準備を進めましょう。
- 財産目録の作成:預貯金、不動産、有価証券、保険などのプラスの財産だけでなく、ローンや借入金などのマイナスの財産もすべてリストアップします。ネット銀行やサブスクリプションサービスなど、見落としがちな項目も忘れずに記載しましょう。
- 不要な口座・カードの解約:使っていない銀行口座やクレジットカードは、本人が解約するのが最も簡単です。家族の負担を減らすためにも、元気なうちに整理しておきましょう。
- 遺言書の作成:財産の分け方を法的に有効な形で残すには遺言書が不可欠です。エンディングノートに希望を書いても法的拘束力はありません。特に相続トラブルを防ぎたい場合は、専門家(行政書士や公証人)に相談し、法的に確実な「公正証書遺言」を作成するのが最も安心です。
2位:医療・介護の意思決定|自分らしい最期を迎えるために
もしもの時に意思表示ができなくなった場合、どのような医療や介護を受けたいか。その希望を明確にしておくことは、自分自身の尊厳を守ると同時に、家族が重大な決断を下す際の精神的負担を大きく和らげます。
厚生労働省も推進する「人生会議(ACP:アドバンス・ケア・プランニング)」とは、もしもの時に備え、自らが望む医療やケアについて前もって考え、家族や医療・ケアチームと繰り返し話し合い、共有する取り組みです。
- リビング・ウィル(事前指示書)の作成:延命治療を希望するかどうか、どのようなケアを望むかなどを文書で残します。
- 医療情報の整理:持病、アレルギー、かかりつけ医、服用中の薬などの情報をまとめておきます。
- 家族との対話:文書に残すだけでなく、なぜそう思うのかを家族と話し合っておくことが非常に重要です。研究によれば、終末期における家族とのコミュニケーションは、本人と家族双方の心のケアに繋がるとされています。
3位:身辺整理(モノ・デジタル)|物理的・精神的負担を軽くする
遺品整理は、残された家族にとって時間的にも精神的にも大きな負担となります。ある調査では、遺品整理を経験した人の約85%が「故人の生前整理は不十分だった」と感じているというデータもあります。元気なうちに身の回りを整理することで、家族の負担を減らし、自分自身もすっきりとした気持ちで過ごせます。
- モノの整理(断捨離):「要るもの」「要らないもの」「誰かに譲りたいもの」に分けます。片付けのコツは、一度に全てやろうとせず、部屋ごとやカテゴリーごとに少しずつ進めることです。
- デジタル遺品の整理:現代の終活で見逃せないのがデジタルデータです。PCやスマホ内のデータ、SNSアカウント、ネットバンクの口座情報、有料サービスのIDとパスワードなどをリスト化し、信頼できる人にだけ保管場所を伝えておきましょう。放置されたアカウントは個人情報漏洩のリスクもあるため、不要なものは解約しておくことが重要です。
【ランキング4位~7位】次に着手したい4つの準備
最優先事項に目処がついたら、次はこの4つの項目に取り組みましょう。これらは、家族への情報伝達をスムーズにし、より円滑な手続きをサポートします。
4位:エンディングノートの作成|想いを伝えるコミュニケーションツール
エンディングノートは、終活の第一歩として非常におすすめです。遺言書と違って法的効力はありませんが、書式が自由で、自分の想いや情報を幅広く書き残せます。
- 書くべき内容:自分の基本情報、財産リストのありか、医療・介護の希望、葬儀の希望、大切な人へのメッセージ、ペットのことなど。
- 役割:家族への引継ぎ書であり、自分の人生を振り返るきっかけにもなります。何から始めていいか分からない人は、まず市販のエンディングノートを一冊購入し、書けるところから埋めていくと良いでしょう。
5位:葬儀・お墓の準備|希望を形にし、遺族の混乱を防ぐ
葬儀は、人が亡くなってから短期間で多くのことを決めなければならず、遺族にとって大きな負担となります。調査によると、約4割の人が亡くなる前に葬儀社を決めているというデータもあり、事前の準備が重要視されています。
- 決めておくこと:葬儀の形式(一般葬、家族葬など)、規模、呼んでほしい人、遺影写真、宗教・宗派の希望。
- お墓について:従来のお墓だけでなく、樹木葬や散骨、永代供養など選択肢は多様化しています。自分や家族の価値観に合った方法を検討し、希望を伝えておくことが大切です。
6位:連絡先リストの作成|人間関係の整理と伝達
万が一の際に誰に連絡してほしいか、誰に訃報を伝えてほしくないかをまとめておくことは、意外と見落としがちですが重要です。親しい友人、お世話になった方、遠い親戚など、自分にしか分からない人間関係を整理しておきましょう。
- リスト化する情報:氏名、続柄・関係性、住所、電話番号、メールアドレス、そして「訃報を伝えてほしいか」の区分を明記します。
7位:保険・年金の見直し|お金の流れを最適化する
ライフステージの変化に合わせて、加入している生命保険や医療保険が現在の自分に合っているかを見直しましょう。不要な保険を解約すれば、月々の支出を抑えることができます。
- 確認事項:保険証券の保管場所、保険会社名、保険の種類、保険金の受取人などを一覧にしておきます。また、年金手帳や基礎年金番号通知書の保管場所も明確にしておきましょう。
【ランキング8位~10位】余裕があれば進めたい3つのこと
これらの項目は、直接的な手続きの負担軽減というよりは、人生を豊かに締めくくり、自分という存在を家族に残すための活動です。
8位:自分史の作成|人生を振り返り、価値を再発見する
自分史の作成は、自分の人生を客観的に振り返る良い機会になります。楽しかった思い出や苦労した経験を書き出すことで、自己肯定感が高まり、残りの人生をどう生きるかの指針にもなります。家族にとっても、あなたの生きた証を知る貴重な贈り物となるでしょう。
9位:ペットの信託・引継ぎ|大切な家族の一員のために
ペットを飼っている方にとって、自分がいなくなった後のペットの世話は大きな心配事です。信頼できる引継ぎ先を事前に決め、飼育方法や費用についてもしっかりと取り決めておくことが大切です。ペット信託などの制度を利用することも選択肢の一つです。
10位:専門家への相談|一人で抱え込まず、プロの力を借りる
終活には、法律や税金など専門的な知識が必要な場面が多くあります。特に遺言書の作成や相続税対策は、自己判断で行うと無効になったり、かえってトラブルを招いたりする可能性があります。司法書士、行政書士、税理士、終活アドバイザーなど、内容に応じて専門家に相談することで、安心して終活を進めることができます。
終活を進める上での3つの注意点
最後に、終活をスムーズに進めるための心構えを3つご紹介します。
- 完璧を目指さない:終活は一度にすべてを終わらせようとせず、できることから少しずつ始めることが長続きのコツです。
- 家族と対話する:終活は一人で黙々と進めるものではありません。相続に関する後悔の原因として、家族間のコミュニケーション不足が挙げられることも多いです。自分の想いを伝え、家族の意見も聞くことで、より良い終活になります。
- 定期的に見直す:家族構成や資産状況、心境は変化するものです。年に一度など、定期的に内容を見直し、最新の情報に更新しましょう。
まとめ:終活は「より良く生きる」ための道しるべ
今回は、終活で整理すべき項目の重要度ランキングと、その具体的な進め方について解説しました。ランキング上位の「財産整理」「医療・介護の意思決定」「身辺整理」は、家族への負担に直結するため、特に優先して取り組むべき項目です。
しかし、最も大切なのは、終活を「やらなければならない義務」と捉えるのではなく、「自分の人生を見つめ直し、残りの時間を豊かにするための活動」と考えることです。この記事をきっかけに、まずはエンディングノートを開くことから、あなた自身の終活を始めてみてはいかがでしょうか。

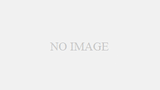
コメント