「自分らしい最期」について、もっと深く考えてみませんか?
LINE公式アカウントにご登録いただくと、終活に関するお役立ち情報や最新のお知らせを定期的にお届けします。
なぜ今、「家族に頼らない終活」が必要なのか?
「終活」という言葉は、もはや特別なものではなくなりました。しかし、その意味合いは時代と共に変化しています。かつては残される家族のために行うもの、という側面が強かった終活ですが、現在は「自分の人生の締めくくり方を自分で決めたい」という、より主体的で前向きな活動として捉えられています。
この背景には、少子高齢化や生涯未婚率の上昇、核家族化といった社会構造の変化があります。日本総研のレポートでも指摘されているように、単身世帯や身寄りのない高齢者は増加傾向にあり、「家族に頼る」ことを前提としない人生設計が誰にとっても現実的な課題となっています。こうした状況から、「おひとりさま」や子どもがいない方々を中心に、家族に頼らず自らの手で万一の事態に備える「一人終活」への関心が高まっているのです。
終活をしない場合に起こりうる4つのリスク
もし、何の準備もしないまま最期の時を迎えたらどうなるのでしょうか。特に頼れる身内がいない場合、以下のような問題が発生する可能性があります。
- 死後の手続きの停滞:死亡届の提出、火葬・埋葬の手配、公共サービスの解約、遺品整理など、死後には膨大な手続きが発生します。担い手がいなければ、これらの手続きが滞り、関係各所に迷惑をかけてしまう恐れがあります。
- 望まない医療・介護:意識がなくなり自分で意思表示できなくなった時、延命治療を望むか否かなど、医療や介護に関する希望を誰も知ることができません。
- 財産の行方不明・意図しない承継:遺言書がなければ、あなたの財産は法律に基づいて相続人が受け取ります。しかし、疎遠な親族や、場合によっては国庫に帰属することになり、お世話になった友人や支援団体へ遺贈したいといった希望は叶えられません。
- 孤独死と発見の遅れ:地域社会との繋がりが希薄な場合、万が一自宅で倒れても誰にも気づかれず、発見が遅れるリスクがあります。これは個人の尊厳に関わる深刻な問題です。
これらのリスクを回避し、最後まで自分らしく、安心して生きるために、元気なうちから準備を進める「一人終活」が極めて重要になるのです。
【完全ガイド】一人で進める終活の5ステップ
「終活」と聞くと、何から手をつければ良いか分からず、途方に暮れてしまうかもしれません。しかし、やるべきことを整理し、一つひとつ着実に進めていけば、決して難しいことではありません。ここでは、家族に頼らない終活を5つのステップに分けて具体的に解説します。
ステップ1:エンディングノートで自分を知る
最初のステップは、自分自身の情報を一元化することです。そのための最適なツールが「エンディングノート」です。遺言書と違って法的効力はありませんが、自分の希望や必要な情報を自由に書き留めることができます。
エンディングノートは、自分自身を振り返り、これからの人生をどう生きたいかを見つめ直すきっかけにもなります。完璧を目指さず、書けるところから少しずつ埋めていくのが続けるコツです。
最低限、以下の項目についてまとめておくと、万一の際に非常に役立ちます。
- 基本情報:氏名、生年月日、本籍地、マイナンバーなど
- 医療・介護の希望:かかりつけ医、持病、アレルギー、延命治療や臓器提供の意思など
- 財産情報:預貯金口座、証券口座、保険、不動産、ローンなどの負債(※口座番号は記載し、暗証番号は書かないこと)
- デジタル情報:PCやスマホのパスワード、契約中のサブスクリプションサービス、SNSアカウントの取扱い
- 葬儀・お墓の希望:希望する形式、連絡してほしい友人リスト、お墓の場所など
- 大切な人へのメッセージ:感謝の言葉や思い出
最近では、自治体がオリジナルのエンディングノートを無料配布しているケースもあります。山口市のように、市民向けに配布している自治体もあるので、お住まいの地域の情報を確認してみるのも良いでしょう。また、紙のノートだけでなく、Googleドキュメントなどのクラウドサービスを活用し、信頼できる人と共有する方法も便利です。
ステップ2:生前整理で「物・心・情報」を整える
エンディングノートで現状を把握したら、次は身の回りを整理していきます。生前整理は単なる「片付け」ではなく、「物」「心」「情報」の3つの側面から捉えることが大切です。
1. 物の整理(断捨離)
楽天インサイトの調査によると、終活で最も関心が高いのは「家の中の荷物整理」(48.1%)でした。物が多すぎると、いざという時に大切なものが見つからなかったり、残された人の負担が大きくなったりします。「1年以上使っていないものは手放す」などのルールを決め、クローゼットやキッチンなど、エリアごとに少しずつ進めるのが効果的です。
2. 情報の整理(デジタル終活)
現代において見過ごせないのが「デジタル遺品」の整理です。パソコンやスマートフォンの中のデータ、SNSアカウント、ネット銀行の口座などは、本人でなければアクセスが困難な場合が多く、放置すると個人情報の流出や不要なサービス料の支払い継続といったトラブルに繋がりかねません。 エンディングノートにアカウント情報やパスワードのヒントを記し、不要なデータやアカウントは定期的に削除する「スマホ終活」を心がけましょう。
ステップ3:法的効力を持つ「契約」で意思を形にする
エンディングノートはあくまで「お願い」であり、法的な拘束力はありません。自分の意思を確実に実現するためには、以下の3つの法的な手続きが重要になります。
1. 遺言書の作成
財産の行方を指定するための最も基本的な手段です。特に、法定相続人以外の人(内縁の妻、友人、お世話になった団体など)に財産を遺したい場合は必須です。政府広報オンラインによると、自筆で作成する場合でも、日付や署名・押印など厳格な要件があり、不備があると無効になるため注意が必要です。不安な場合は、公正証書遺言の作成を検討しましょう。
2. 死後事務委任契約
これは「一人終活」の要とも言える契約です。自分が亡くなった後の諸手続き(役所への届出、葬儀・納骨、遺品整理、各種契約の解約など)を、信頼できる第三者(友人、司法書士、NPO法人など)に委任する契約です。弁護士法人ベリーベスト法律事務所の解説にもあるように、この契約を締結しておくことで、死後の不安を大幅に軽減できます。トラブルを避けるため、契約内容は公正証書にしておくことが強く推奨されます。
3. 任意後見契約・家族信託
認知症などで判断能力が低下した「生前」に備えるための制度です。
- 任意後見契約:元気なうちに、将来判断能力が不十分になった場合に備えて、財産管理や身上監護の事務を代行してもらう人(任意後見人)をあらかじめ決めておく契約です。
- 家族信託:財産の管理や処分を、信頼できる家族や第三者に託す契約です。より柔軟な財産管理が可能になります。
これらの契約は複雑なため、司法書士や弁護士などの専門家に相談しながら進めるのが賢明です。
ステップ4:頼れる「人」と「サービス」を見つける
法的な準備と並行して、日々の安心を確保し、いざという時に頼れる体制を築くことも重要です。
高齢者見守りサービス
孤独死のリスクを軽減するために有効なのが、民間の見守りサービスです。センサーで人の動きを検知するタイプ、定期的に電話や訪問があるタイプ、緊急時にボタン一つで通報できるタイプなど様々です。費用やサービス内容も多岐にわたるため、自分のライフスタイルや予算に合ったものを選びましょう。
※上記グラフは複数のサービス比較サイトの情報を基に作成した目安です。実際の料金は各社にご確認ください。
身元保証サービス
賃貸住宅への入居や病院への入院・入所時に必要となる「身元保証人」を代行してくれるサービスです。死後事務手続きをセットで提供している法人も多く、おひとりさまの強力な味方となります。
ステップ5:終活にかかる費用を把握し、準備する
終活には、ある程度の費用がかかります。事前に全体像を把握し、資金計画を立てておくことが大切です。 ハルメク 生きかた上手研究所の2025年の調査によると、終活にかかった費用の平均は約503万円という結果が出ています。これは、お墓の購入や整理、葬儀代などが含まれるため高額になっていますが、内訳は人それぞれです。
- 生前の準備費用:遺言書作成や各種契約の相談料(司法書士・弁護士など)、公正証書作成費用(数万円〜十数万円)
- 死後の費用:死後事務委任契約の報酬(委任内容により50万円〜100万円以上)、葬儀費用、お墓・納骨費用など
自分の希望を叶えるためにどれくらいの費用が必要か、専門家や葬儀社に相談し、見積もりを取っておくと安心です。
一人で抱え込まないために:専門家とコミュニティの活用
「一人で進める」といっても、すべてを自分一人で完結させる必要はありません。むしろ、積極的に外部の力や繋がりを頼ることが、成功の鍵となります。
信頼できる専門家への相談
法律や税金が関わる手続きは、素人判断で行うと後々トラブルになりかねません。財産整理や相続、各種契約については、司法書士や弁護士、税理士といった専門家に相談しましょう。初回相談を無料で行っている事務所も多いため、まずは気軽に問い合わせてみることをお勧めします。
自治体の支援サービスと終活イベント
多くの自治体では、高齢者や単身者向けの終活支援に力を入れています。ジチタイワークスの記事でも紹介されているように、その内容は多岐にわたります。
- 終活相談窓口の設置
- エンディングノートの無料配布
- 終活セミナーや講座の開催
- 高齢者の安否確認(見守り)サービスとの連携
お住まいの市区町村の役所の高齢者福祉課や、地域包括支援センターに問い合わせてみましょう。また、葬儀社や石材店、NPO法人が主催する終活イベントやセミナーも、情報収集や専門家と直接話せる良い機会です。
「終活仲間」という新しい繋がり
同じ悩みや関心を持つ人との繋がりは、大きな心の支えになります。地域のサークルや趣味の集まりに参加するだけでなく、最近では「終活」をテーマにしたコミュニティも増えています。
こうした場では、エンディングノートの書き方を教え合ったり、身元保証サービスの情報交換をしたりと、前向きに将来の準備について語り合うことができます。孤独感を和らげ、有益な情報を得られるだけでなく、新たな友人関係が生まれることも少なくありません。
まとめ:自分らしい最期を迎えるための第一歩
家族に頼らない終活は、「死」の準備というネガティブなものではなく、「人生の最後まで自分らしく、安心して生きる」ためのポジティブな活動です。エンディングノートで自分を見つめ直し、生前整理で身軽になり、法的な契約で意思を確かなものにする。そして、専門家や地域社会、新しい仲間との繋がりを築く。この一連のプロセスは、残りの人生をより豊かに、主体的に生きるための道しるべとなるでしょう。
この記事でご紹介したステップを参考に、まずはエンディングノートを開くことから始めてみませんか。一人で抱え込まず、様々なサービスや人を頼りながら、あなただけの「納得のいくエンディング」をデザインしていきましょう。
終活の第一歩、私たちと一緒に踏み出しませんか?
LINE公式アカウントでは、終活セミナーのお知らせや、専門家によるコラムなど、あなたの「これから」に役立つ情報を発信しています。

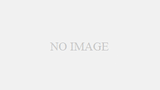
コメント