終活は「いつから始めればいい?」その疑問に答えます
「終活」という言葉を耳にする機会は増えたものの、「具体的にいつから、何から手をつければいいのか分からない」「自分にはまだ早い気がする」「死の準備なんて、縁起でもない…」と感じ、一歩を踏み出せずにいる方は少なくないでしょう。あるいは、考え始めると漠然とした不安に襲われ、つい後回しにしてしまう、という方もいらっしゃるかもしれません。そのお気持ち、非常によく分かります。
しかし、終活は決してネガティブなものではありません。むしろ、これからの人生をより自分らしく、安心して、そして豊かに生きるための「前向きな準備」です。この記事では、そんな終活に対する漠然とした疑問やためらいを解消し、あなたにとって本当に最適なスタートのタイミングを見つけるお手伝いをします。年代ごとに「何をすべきか」を具体的に解き明かし、あなたが今日からできること、そして未来のために準備すべきことを明確にするための完全ガイドです。
結論から申し上げますと、終活を始めるのに「早すぎる」ということは決してなく、「思い立ったその時」があなたにとってのベストタイミングです。なぜなら、私たちのライフステージや価値観は一人ひとり異なり、画一的な「適齢期」は存在しないからです。ただし、年齢やライフステージに応じて、取り組むべきことの優先順位や内容は変わってきます。この記事を最後までお読みいただければ、漠然とした不安は具体的な行動計画へと変わり、これからの人生を設計する、希望に満ちた第一歩を踏み出せるはずです。
【LINE登録のご案内】
終活に関するさらに詳しい情報や、専門家からのお役立ち情報、お得なお知らせを受け取りたい方は、ぜひ合同会社KUREBAのLINE公式アカウントにご登録ください。あなたの終活を力強くサポートします。
そもそも終活とは?人生を豊かにするための前向きな活動
「終活」と聞くと、どうしても「死への準備」という少し重いイメージが先行しがちです。しかし、現代における終活の意味合いは大きく変化し、よりポジティブで広範な活動を指すようになっています。
現代における終活の定義
現代の終活は、単に葬儀やお墓の準備をすることだけではありません。それは、「人生の終わりを穏やかに迎えるために、これまでの人生を振り返り、整理し、これからの生き方を計画する、包括的で前向きな活動」と再定義できます。博報堂100年生活者研究所が提唱するように、それは「人生終い支度」から「人生再設計支度」へと進化しているのです。
「人生100年時代」と言われる現代において、定年後の時間はもはや「余生」ではなく、人生のセカンドステージ、あるいはサードステージです。この長い時間をいかに自分らしく、心豊かに過ごすか。そのための「人生の棚卸し」であり、「未来設計図の作成」こそが、現代の終活の本質と言えるでしょう。具体的には、医療や介護、財産管理、人間関係、そして自分の価値観に至るまで、幅広いテーマについて考え、自分の意思を明確にしていくプロセス全体を指します。
終活がもたらす3つの大きなメリット
終活に取り組むことは、自分自身だけでなく、大切な家族にとっても計り知れないメリットをもたらします。主なメリットを3つの側面に分けて見ていきましょう。
1. 残される家族の負担を劇的に減らせる
万が一の時、残された家族は深い悲しみの中で、数多くの判断と手続きに追われることになります。葬儀の形式や規模はどうするか、お墓はどうするのか、誰に連絡すればよいのか、大切な遺品をどう整理すればよいのか――。これらの問いに一つひとつ答えていくのは、精神的にも物理的にも非常に大きな負担です。ある調査では、親が存命の子どもの65%以上が「エンディングノートを残してほしい」と回答しており、家族が情報や希望を求めていることがわかります。事前にエンディングノートや遺言書で自分の希望を明確に伝えておけば、家族は迷うことなく手続きを進めることができ、その負担を劇的に軽減できます。これは、家族への最後の、そして最大の思いやりと言えるでしょう。
2. 相続をめぐるトラブルを未然に防げる
「うちは財産なんてないから大丈夫」「家族の仲は良いから揉めるはずがない」。そう思っていても、相続がきっかけで家族関係に亀裂が入ってしまうケースは後を絶ちません。問題は財産の大小ではなく、誰が何をどれだけ相続するのかが不明確であること、そして故人の意思が分からないことに起因します。終活の一環として、自分の資産(預貯金、不動産、有価証券など)と負債(ローンなど)を正確にリストアップし、財産目録を作成しておくこと。そして、法的に有効な遺言書で分配方法を指定しておくことは、相続トラブルを防ぐための最も確実な方法です。家族が「争続」で心を痛めることのないよう、道筋を立てておくことは非常に重要です。
3. 自分の人生を振り返り、未来をより豊かにできる
終活の最も素晴らしいメリットは、実は「これからの人生」が豊かになる点にあります。自分の持ち物や人間関係、財産を整理する過程は、まさに「人生の棚卸し」です。これまでの歩みを振り返る中で、「自分にとって本当に大切なものは何だったのか」「誰に感謝を伝えたいのか」「これから何をしたいのか」といった、自身の本質的な価値観や願望に改めて気づかされます。エンディングノートを書くことは、自分の価値観を整理し、これからの人生をより前向きに生きるための指針を明確にする作業でもあります。死を意識することは、同時に「生」を強く意識することにつながります。残された時間をどう輝かせるか、新たな目標や楽しみを見つけるきっかけとなり、人生の最終章をより充実させる原動力となるのです。
【結論】終活のベストタイミングは「思い立ったとき」。でも、きっかけは?
多くの専門家やメディアが「終活はいつから始めるべきか」という問いに対し、「興味を持ったときが適切なタイミング」だと口を揃えます。これは決して無責任な回答ではなく、終活の本質を捉えた真理です。では、なぜ「思い立ったとき」がベストタイミングなのでしょうか。その理由と、多くの人が実際に終活を意識し始める「きっかけ」について深掘りしていきます。
なぜ「思い立ったとき」が最適なのか
画一的な年齢基準ではなく、個人の「思い立ったとき」を推奨するのには、明確で合理的な理由が3つあります。
理由1:健康で判断能力が十分なうちに
終活は、自分の人生に関する重要な決断の連続です。財産の分配、医療や介護の方針、葬儀の希望など、自分の意思を正確に反映させるためには、心身ともに健康で、冷静かつ客観的な判断ができる状態であることが不可欠です。年齢を重ねると、認知症やその他の病気によって判断能力が低下するリスクは誰にでもあります。判断能力を喪失してしまうと、遺言書の作成や任意後見契約といった重要な法律行為ができなくなってしまいます。元気な「今」だからこそ、自分の本当の望みを考え、形に残すことができるのです。「まだ大丈夫」と先延ばしにせず、判断能力が十分なうちに始めることが、後悔しないための最大の秘訣です。
理由2:ライフプランは人それぞれ
「65歳で定年退職し、子どもは独立済み」といった、かつての標準的なライフモデルは過去のものとなりつつあります。働き方、家族の形、価値観が多様化した現代において、人生の節目は人によって大きく異なります。ある人にとっては50代での早期退職が転機かもしれませんし、別の人にとっては40代での子どもの結婚がきっかけになるかもしれません。ライフプランは人によって異なるため、「何歳」という部分に固執する必要はないのです。他人の基準に合わせるのではなく、ご自身の仕事や家庭の状況、価値観といったライフプランの変化に合わせて、「そろそろ考えてみようか」と思ったその瞬間こそが、あなたにとって最も合理的で自然なスタートタイミングなのです。
理由3:予期せぬ事態への備え
私たちは、明日何が起こるかを予測することはできません。病気や不慮の事故は、年齢に関係なく誰の身にも起こりうるものです。早く始めることで、不慮の事故や予期せぬ病に備えることができます。特に20代や30代といった若い世代にとっては、「終活」は死の準備というより「万が一に備えるライフプランニング」の一環と捉えることができます。もしもの時に家族が困らないようにデジタル資産の情報をまとめておいたり、自分の医療に関する希望を書き留めておいたりすることは、年齢に関わらず重要です。先延ばしにせず、「思い立ったとき」に行動することで、未来の不確実性に対する安心感を得ることができます。
多くの人が終活を意識する「3つのきっかけ」
「思い立ったとき」がベストタイミングである一方、多くの人が具体的に終活を意識し始めるのには、共通した「きっかけ」が存在します。ご自身がこれらの状況に当てはまるなら、それは終活を始める良い機会かもしれません。
① ライフステージの変化
人生の大きな節目は、自分自身を振り返る絶好の機会となります。最も代表的なのが定年退職です。65歳頃に終活を始める人が多い理由の一つは、仕事から解放され、自分の時間が増えることです。また、子どもの結婚や独立も大きなきっかけです。子育てという大きな役割を終え、自分の将来や夫婦二人の老後についてじっくり考える時間が生まれます。これらの変化は、第二の人生のプランを立てる上で、自然と終活へと意識を向かわせるのです。
② 周囲の変化
自分自身の変化だけでなく、身の回りの人々の変化も、終活を始める大きな動機となります。特に、親の介護や他界を経験することは、多くの人にとって「死」や「老い」を自分ごととして捉える強烈な体験となります。親の遺品整理の大変さや、相続手続きの煩雑さを目の当たりにし、「自分の子どもには同じ苦労をさせたくない」と強く感じるのです。また、同年代の友人・知人の病気や訃報に接したときも同様です。「自分もいつ何があるか分からない」という現実を突きつけられ、将来への備えの必要性を痛感するきっかけとなります。
③ 自身の健康の変化
体は正直です。若い頃のように無理がきかなくなったり、健康診断で思わしくない結果が出たり、あるいは大きな病気を患ったりすると、誰しも将来への具体的な不安を抱きます。体力の衰えを感じ始めると、「元気なうちに、動けるうちにやっておかなければ」という気持ちが強くなります。病気の診断を受けた場合は、治療方針や延命措置に関する自分の希望を明確にしておきたいという切実な思いが生まれます。こうした自身の健康状態の変化は、先延ばしにしていた終活に、真剣に向き合うための直接的なきっかけとなるのです。
【年代別】後悔しないための終活スタートガイド&やることリスト
終活は「思い立ったが吉日」ですが、年代やライフステージによって直面する課題や準備すべきことの優先順位は異なります。ここでは、各年代の特性に合わせた終活の意義と、具体的な「やることリスト」を詳しく解説します。ご自身の年代はもちろん、他の年代の状況も知ることで、より長期的で包括的な視点から終活を捉えることができるでしょう。
各種調査では、定年などを迎える60代で終活を意識し始める人が最も多い傾向が見られます。
20代・30代:「未来への投資」として始める超早期終活
20代や30代で「終活」と聞くと、ほとんどの方が「早すぎる」と感じるでしょう。しかし、この年代の終活は「死の準備」という側面よりも、「人生設計をより明確にし、豊かにするための自己分析ツール」としての意味合いが非常に強いのが特徴です。いわば、未来の自分への「投資」と捉えることができます。
若いうちに将来の目標や理想像を具体的に描くことで、人生設計がクリアになるという大きなメリットがあります。自分の価値観と向き合い、万が一に備えることで、日々の生活をより意識的に、そして前向きに過ごすことができるようになります。
やることリスト
- エンディングノート(ライト版)の作成:本格的なものではなく、自分史や自己紹介ノートを作る感覚で始めてみましょう。自分の基本情報(氏名、生年月日、本籍地など)、学歴、職歴、好きな音楽や映画、大切な人への感謝のメッセージなどを書き留めます。これは自分のキャリアやライフプランを見直すきっかけにもなり、自分という人間を客観的に見つめ直す良い機会になります。
- デジタル資産の棚卸し:現代人にとって避けて通れないのがデジタル資産の管理です。SNSアカウント、オンラインバンキング、各種サブスクリプションサービス、クラウド上の写真データなど、その種類と量は増え続ける一方です。これらのIDとパスワードをリスト化し、万が一の際に家族がアクセス・解約できるよう整理しておくことは、デジタル終活の第一歩として非常に重要です。安全なパスワード管理アプリの利用も検討しましょう。
- 資産形成の開始:終活は「お金」の問題と密接に関わっています。若いうちから資産形成を始めることは、将来の経済的な自由と安心に直結します。つみたてNISAやiDeCoといった税制優遇制度を活用し、少額からでもコツコツと積立投資を始めることをお勧めします。これは老後資金のためだけでなく、自分の夢を実現するための資金作りでもあります。
- 保険の見直し・加入検討:若くて健康なうちは保険の必要性を感じにくいかもしれませんが、病気や怪我は予測できません。万が一、長期の入院や就業不能状態になった場合に、自分や家族の生活を守るための備えは必要です。現在の公的保障でカバーされる範囲を理解した上で、自分にとって必要な医療保険や就業不能保険は何かを検討する良い機会です。
40代・50代:「人生の棚卸し」と「親の終活」を考える現実的終活
40代・50代は、まさに人生の折り返し地点。仕事では責任ある立場になり、家庭では子どもの教育や独立、そして親の高齢化といった課題に直面する、非常に多忙な時期です。この年代は、親の老いと自分の老後を同時に考える「ダブルケア」の分岐点に立つことが多く、終活が非常に現実的なテーマとして浮上してきます。
体力・気力・判断力が充実しているこの時期は、腰を据えて終活に取り組むのに最適な「ゴールデンタイム」とも言えます。親の介護や相続を経験することで「自分ごと」として捉えやすくなり、具体的で実践的な準備を進めることができます。
やることリスト
- 親の終活サポートと意思確認:親の終活は、決して子どもが主導するものではありません。しかし、親が元気なうちにコミュニケーションを取り、その意思を確認しておくことは極めて重要です。介護が必要になったらどこで過ごしたいか、延命治療は望むか、葬儀はどのようにしてほしいかなど、さりげない会話の中から希望を聞き出しましょう。エンディングノートをプレゼントして、一緒に書いてみるのも良い方法です。
- 老後資金のリアルな計画:「ねんきん定期便」などで将来の年金受給見込み額を確認し、理想の老後生活にいくら必要か、具体的なシミュレーションを行いましょう。富田林市のガイドブックが指摘するように、70代で資金不足に気づくより、50代で気づいた方が対策を講じる時間があります。現在の資産状況を把握し、必要であれば資産運用のポートフォリオを見直したり、退職金の運用計画を立てたりすることが重要です。
- 医療・介護の希望の明確化:自分が病気で意思表示できなくなった場合に備え、どのような医療やケアを望むか(あるいは望まないか)を文書で示しておく「リビング・ウィル(事前指示書)」の検討を始めましょう。また、介護が必要になった場合に在宅介護を望むのか、施設への入居を希望するのか、その費用は誰がどのように負担するのかなど、具体的な希望を家族と話し合い、記録しておくことが大切です。
- 本格的な断捨離(生前整理):「老前整理」とも呼ばれるこの時期の片付けは、体力があるうちにしかできない重要な作業です。長年溜め込んだ家財や衣類、趣味の道具などを見直し、不要なものを処分します。これは単なる片付けではなく、日々を真剣に生きていくために身の回りを整える行為であり、残される家族の遺品整理の負担を大幅に軽減することにも繋がります。思い出の品の整理には時間がかかるため、早めに着手することが推奨されます。
60代:「第二の人生の設計」と具体的な手続きを進める本格的終活
60代は、定年退職を迎え、多くの人が時間に余裕を持つようになる時期です。前述の調査データが示すように、実際に終活を始める人が最も多いボリュームゾーンであり、社会的な関心もこの年代に集中しています。体力や判断力もまだ十分に残っている場合が多く、相続といった法的な手続きも含め、具体的かつ本格的な準備を進めるのに最適なタイミングと言えます。
この年代の終活は、「第二の人生をどう楽しむか」というポジティブな設計と、「もしもの時」への具体的な備えを両輪で進めていくことが特徴です。
やることリスト
- 財産目録の作成:預貯金(銀行名、支店名、口座番号)、不動産(所在地、面積、名義)、有価証券(株式、投資信託など)、保険(保険会社、証券番号)、そしてローンや借入金といった負債まで、すべての資産を一覧にした「財産目録」を作成します。これは相続手続きをスムーズに進めるための基礎資料となり、遺言書を作成する上でも不可欠です。現状を正確に把握することで、相続税対策の必要性なども見えてきます。
- 遺言書の作成検討:財産目録を基に、誰にどの財産を遺したいのか、具体的な意思を法的に有効な形で残すために遺言書の作成を検討します。主に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。自筆証書遺言は手軽ですが要件が厳しく無効になるリスクも。一方、公正証書遺言は費用と手間がかかりますが、公証人が作成に関与するため最も確実性が高く、相続トラブルを強力に防ぐ効果があります。専門家(弁護士、司法書士、行政書士など)に相談しながら進めるのが賢明です。
- 葬儀・お墓の希望決定:自分が望む最後のセレモニーについて、具体的な希望を固めていきましょう。葬儀の形式(一般葬、家族葬、一日葬、直葬など)、規模、場所、費用について情報収集し、家族に伝えます。また、埋葬方法についても、従来のお墓だけでなく、納骨堂、樹木葬、散骨など多様な選択肢があります。それぞれのメリット・デメリットを比較検討し、自分の価値観に合った方法を選び、その意思をエンディングノートなどに記しておきましょう。
- 連絡先リストの作成:いざという時に家族が連絡に困らないよう、親戚、友人、知人、お世話になった方々の連絡先(氏名、住所、電話番号、関係性など)をリストアップしておきます。特に、葬儀に参列してほしい人については、その旨を明記しておくと良いでしょう。これは遺品整理の負担を減らすだけでなく、故人との縁を大切にする上でも重要な作業です。
70代以上:「安心」のための最終確認とアップデート
70代以上になると、多くの方がこれまでの人生で何らかの形で終活の準備を進めてきているかもしれません。この年代における終活のテーマは、新たなことを始めるというよりは、これまでの準備内容を見直し、心穏やかに日々を過ごすための「総仕上げ」と「メンテナンス」です。
心身機能の変化を念頭に置きながら、作成済みの書類が現状に合っているかを確認し、情報を最新の状態に保つこと。そして、その内容を家族と確実に共有し、本人も家族も「安心」できる状態を作ることが最も重要になります。
やることリスト
- 各種書類の見直しと更新:エンディングノート、遺言書、財産目録などの内容は、時間の経過とともに現状とそぐわなくなることがあります。例えば、資産状況の変化、家族構成の変化(孫の誕生など)、あるいは自身の心境の変化などです。少なくとも年に一度は内容を見直し、変更点があれば修正・更新する習慣をつけましょう。特に遺言書は、法的な要件を満たした形で修正する必要があります。
- 身の回りの最終整理:60代までにある程度の断捨離を終えていたとしても、身の回りのものは少しずつ増えていきます。日々の生活に支障のない範囲で、不要なものの整理を続けましょう。特に、思い出の品(写真、手紙、趣味の作品など)の整理は、この年代の重要なテーマです。すべてを捨てる必要はありません。デジタル化して保存する、特に大切なものだけを「思い出ボックス」にまとめる、誰に何を形見分けとして遺したいかを具体的にリストアップするなど、保管方法を工夫することが大切です。
- 医療・介護の希望の再確認と共有:健康状態は変化するものです。以前にリビング・ウィルなどで意思表示をしていたとしても、現在の自分の気持ちを改めて確認することが重要です。かかりつけの医師や、日常的に関わる家族、キーパーソンとなる人物と、延命治療や終末期医療に関する希望を再度話し合い、意思を共有しておきましょう。「最後まで自分らしく生きるため」というポジティブな目的を共有することで、家族もその意思を尊重しやすくなります。
- 専門家との連携:相続や不動産の問題でお世話になった税理士、司法書士、弁護士などがいる場合は、その連絡先をまとめたリストを作成し、家族に渡しておきましょう。万が一の際に、誰に相談すればよいかが分かっているだけで、家族の不安は大きく軽減されます。信頼できる専門家との繋がりを、家族に引き継いでおくことも大切な終活の一つです。
終活で後悔しないために。スムーズに進める3つのコツ
終活の必要性を理解し、年代別のやるべきことを把握しても、いざ始めるとなると「何から手をつければ…」「大変そう…」と足踏みしてしまうことがあります。終活で求められる作業は多岐にわたるため、途中で挫折しないためにも、自分のペースで進めることが重要です。ここでは、終活をスムーズに進め、後悔しないための3つの実践的なコツをご紹介します。
1. 完璧を目指さず、できることから始める
終活は、一度にすべてを終わらせなければならない壮大なプロジェクトではありません。「遺言書も書いて、断捨離もして、お墓も決めて…」と最初から完璧を目指すと、そのタスクの多さに圧倒され、かえってやる気を失ってしまいます。大切なのは、小さな一歩を踏み出すことです。
「まずはエンディングノートを1冊買ってみる」「今日は引き出しを1段だけ片付けてみる」「自分の銀行口座をリストアップしてみる」など、ほんの少しの時間でできることから始めてみましょう。気負わずに、日々の暮らしの中で自然に取り組むことが、長続きの秘訣です。一つクリアできれば自信になり、次のステップに進む意欲が湧いてきます。
2. 一人で抱え込まず、家族とオープンに話す
終活は、自分のためだけに行うものではありません。むしろ、大切な家族への「愛情表現」の一つです。自分の死後、家族に迷惑をかけたくない、悲しみの他に余計な負担を背負わせたくない、という想いが根底にあるはずです。それならば、その想いを家族に伝え、一緒に準備を進めるのが最も良い方法です。
もちろん、「死」に関する話題は切り出しにくいものです。「親の終活」のセクションでも触れましたが、「最近、友人が親の相続で大変だったみたいで…」「この間テレビでエンディングノートの特集をやっていてね」など、第三者の話やメディアの情報をきっかけにすると、自然に会話を始めやすいでしょう。自分の想いや希望をオープンに話すことで、家族はあなたの考えを理解し、安心することができます。それは家族とのコミュニケーションを深め、絆を再確認する貴重な機会にもなるのです。
3. 専門的なことはプロに相談する
終活には、自分や家族だけで解決できることもあれば、専門的な知識が不可欠な分野もあります。特に、相続税の計算、不動産の登記、法的に有効な遺言書の作成などは、素人判断で進めると後々大きなトラブルに発展しかねません。
こうした専門分野については、決して無理をせず、それぞれのプロフェッショナルに相談することを強くお勧めします。税理士、司法書士、弁護士、行政書士、ファイナンシャルプランナーなど、信頼できる専門家に並走してもらうことで、手続きは正確かつスムーズに進みます。相談費用はかかりますが、間違った手続きによる将来的な損失や、家族間のトラブルを回避できることを考えれば、それは必要不可欠な投資と言えるでしょう。結果的に、時間と労力を節約し、最も確実で安心な方法となるのです。
まとめ:最高のタイミングで終活を始め、これからの人生をもっと輝かせよう
この記事では、「終活をいつから始めるべきか」という問いを軸に、その本質から具体的な進め方までを多角的に解説してきました。最後に、重要なポイントを改めて振り返ります。
この記事のキーポイント
- 終活は「死の準備」ではなく、残りの人生を自分らしく豊かに生きるための前向きな活動です。家族の負担軽減やトラブル防止だけでなく、自分自身の未来を輝かせる効果があります。
- 終活を始めるのに最適なタイミングは、年齢で区切られるものではなく、「思い立った今」です。健康で判断能力が十分なうちに、自分のライフプランに合わせて始めるのが最も合理的で、早すぎるということは決してありません。
- 年代ごとに取り組むべき課題や優先順位は異なります。20代・30代は「未来への投資」、40代・50代は「人生の棚卸し」、60代は「具体的な手続き」、70代以上は「安心のための総仕上げ」と、それぞれのステージに合った準備を進めることが成功の秘訣です。
- 完璧を目指さず、できることから少しずつ、そして一人で抱え込まずに家族と話し合いながら進めることが、挫折しないためのコツです。専門的なことは迷わずプロに相談しましょう。
終活は、決して暗く、後ろ向きな作業ではありません。むしろ、自分の人生と真剣に向き合い、大切な人への感謝と愛情を形にする、尊い時間です。この記事が、あなたが抱えていた終活への漠然とした不安を解消し、前向きな一歩を踏み出すきっかけとなれば、これほど嬉しいことはありません。
未来の自分のため、そして何よりも大切な家族のために。今日からできる、小さな一歩を始めてみませんか。あなたのこれからの人生が、より一層輝かしいものになることを心から願っています。
【今すぐご登録を!】
終活の準備、一人で悩んでいませんか?合同会社KUREBAのLINE公式アカウントでは、終活のやることリスト、専門家による解説、法改正などの最新情報を定期的にお届けします。以下のリンクから友だち追加して、後悔しないための準備を始めましょう!

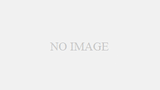
コメント