終活は「これからの人生」を豊かにする活動
「終活」という言葉を聞くと、少し身構えてしまうかもしれません。しかし、終活は単なる「死への準備」ではありません。自分の人生を振り返り、残りの時間をどう生きるかを見つめ直すことで、これからの毎日をより前向きで、心豊かに過ごすためのポジティブな活動です。
近年、少子高齢化やライフスタイルの多様化を背景に、終活への関心が高まっています。元気なうちに自分の意思を整理し、家族に伝えておくことは、万一の時に家族の精神的・物理的な負担を大きく軽減することにつながります。この記事では、終活を始めたいけれど「何から手をつければいいかわからない」という初心者の方に向けて、最初にやるべき5つのステップを具体的に解説します。
ステップ1:エンディングノートの作成 – 自分の想いを「見える化」する
終活の第一歩として最も手軽に始められるのが「エンディングノート」の作成です。まずは自分の考えや希望を書き出すことで、頭の中を整理し、次に何をすべきかが見えてきます。
エンディングノートとは?遺言書との違い
エンディングノートは、自分の人生の記録や、万一の時に家族に伝えたいことを書き留めておくノートです。市販のノートや法務省が提供するテンプレートなど、様々な形式がありますが、基本的には自由に書くことができます。重要なのは、エンディングノートには遺言書のような法的な効力はないという点です。しかし、自分の意思を家族に伝えるための重要なコミュニケーションツールとなります。
エンディングノートは、自分の考えを整理したり家族に意思を伝えたりといった目的があります。記載内容・方法にルールもなく、メモ帳に近い感覚で記録と要望を残せる方法です。
何をどう書く?具体的な項目例
エンディングノートに決まった形式はありませんが、一般的に以下のような項目を記載します。すべてを一度に埋めようとせず、書けるところから少しずつ書き進めていきましょう。
- 自分自身の基本情報:本籍地、マイナンバー、パスポート情報など
- 資産について:預貯金口座、有価証券、不動産、保険、ローンなどの一覧
- 医療・介護について:延命治療の希望、かかりつけ医、アレルギー情報、介護してほしい場所など
- 葬儀・お墓について:希望する葬儀の形式や規模、連絡してほしい友人リスト、お墓の希望
- 大切な人へのメッセージ:家族や友人への感謝の言葉や伝えたい想い
- ペットについて:もしもの時に世話をお願いしたい人、かかりつけの動物病院など
法務省も終活の一助としてエンディングノートの様式を提供しており、参考にしてみるのも良いでしょう。
ステップ2:財産整理 – 「モノ」と「お金」の現状を把握する
自分の財産を整理し、全体像を把握することは、相続トラブルを防ぎ、残された家族の負担を減らすために非常に重要です。財産には、物品などの「モノ」と、預貯金や不動産などの「お金」の両方が含まれます。
モノの整理(生前整理):心も空間もスッキリ
生前整理とは、元気なうちに身の回りの物を整理することです。目的は、残された家族が遺品整理で苦労しないようにすることですが、不要な物を手放すことで、現在の生活空間が快適になり、心も軽くなるというメリットもあります。
- 判断基準を持つ:「1年以上使っていないもの」「今後使う予定がないもの」など、自分なりのルールを決めて仕分けをしましょう。
- 少しずつ進める:一度に全てを片付けようとせず、「今日はこの引き出しだけ」というように、小さな範囲から始めるのが継続のコツです。
- 思い出の品:無理に捨てる必要はありません。家族と一緒に写真を見ながら思い出を語り合うなど、大切な時間に変えることもできます。
お金の整理:資産リストで相続をスムーズに
相続は、プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も引き継がれます。相続手続きを円滑に進めるため、自分の資産を一覧にした「財産目録」を作成しましょう。
相続の対象となるのは「全ての資産、権利、義務」です。注意点は、現預金、不動産といった「プラスの財産」だけでなく、借入金、未払金といった「マイナスの財産」も含まれるということです。
エンディングノートに書き出す形で、以下の情報をまとめておくと、家族が手続きをする際に非常に助かります。
- プラスの財産:銀行名・支店名・口座番号、生命保険の会社名・証券番号、不動産の所在地、有価証券の情報など。
- マイナスの財産:住宅ローン、カードローンなどの借入先と残高。
忘れてはいけない「デジタル遺産」
現代では、スマートフォンやパソコンの中にも多くの資産が存在します。これらは「デジタル遺産」と呼ばれ、近年その整理の重要性が増しています。
- 金融資産:ネット銀行、ネット証券、仮想通貨(暗号資産)など。
- 情報資産:SNSアカウント、ブログ、有料のサブスクリプションサービスなど。
IDやパスワードが分からないと、家族は存在に気づくことすらできず、解約手続きも困難になります。エンディングノートなどにアカウント情報をリストアップし、保管場所を信頼できる家族に伝えておくことが重要です。
ステップ3:医療・介護の希望を明確にする – 自分らしい最期のために
もしもの時、自分がどのような医療や介護を受けたいか。これは非常にデリケートですが、重要な問題です。判断能力があるうちに自分の意思を明確にし、家族と共有しておくことで、いざという時に家族が難しい決断を迫られるのを避けることができます。
- 延命治療の希望:人工呼吸器や胃ろうなど、回復の見込みがない場合の延命措置を希望するかどうか。
- 告知の希望:がんなどの重い病気になった場合、病名や余命を知りたいかどうか。
- 介護の希望:介護が必要になった場合、自宅で過ごしたいのか、施設に入りたいのか。
これらの希望は、エンディングノートに記すだけでなく、日頃から家族と話し合っておくことが最も大切です。終活をきっかけに、親子や夫婦で真剣に話し合う時間は、お互いの理解を深め、絆を強める機会にもなります。
ステップ4:葬儀・お墓の希望を決める – 家族の負担を軽くする
葬儀やお墓は、残された家族が最初に対応を迫られる大きな事柄です。費用も高額になりがちなため、生前に自分の希望を伝え、準備を進めておくことで、家族の金銭的・精神的負担を大幅に軽減できます。
多様化する葬儀のスタイル
かつては多くの弔問客を招く「一般葬」が主流でしたが、現在はより小規模で多様な葬儀スタイルが選ばれています。
- 家族葬:家族や親しい友人など、ごく近しい人だけで行う小規模な葬儀。
- 一日葬:お通夜を行わず、告別式と火葬を一日で済ませる形式。
- 直葬(火葬式):儀式を行わず、火葬のみを行う最もシンプルな形式。
どのような規模で、誰を呼び、どのような雰囲気で見送られたいか、自分の希望を考えてみましょう。葬儀社から事前に見積もりを取っておくことも有効です。
参考:葬儀費用の全国平均
葬儀にはまとまった費用が必要です。2024年の調査によると、葬儀費用の総額の平均は約120万円前後となっています。内訳を把握し、どの部分に費用をかけたいかを考えておくことが大切です。
お墓の選択肢もさまざま
お墓についても、伝統的な家のお墓以外に様々な選択肢が登場しています。
- 永代供養墓:お寺や霊園が家族に代わって遺骨を管理・供養してくれるお墓。承継者がいない場合でも安心です。
- 納骨堂:屋内に設けられた、遺骨を納めるための施設。天候に左右されずお参りしやすいのが特徴です。
- 樹木葬:墓石の代わりに樹木をシンボルとするお墓。自然に還りたいという方に選ばれています。
元気なうちに資料請求をしたり、実際に霊園を見学したりして、自分や家族に合った形を検討しておくと良いでしょう。
ステップ5:遺言書の作成 – 法的効力のある意思表示
終活の総仕上げともいえるのが「遺言書」の作成です。エンディングノートが「想い」を伝えるものであるのに対し、遺言書は財産の分け方などについて法的な効力を持たせるための重要な書類です。
遺言書が持つ法的な力
遺言書がない場合、遺産は法律で定められた相続人(法定相続人)が、法律で定められた割合(法定相続分)で分けるか、相続人全員での話し合い(遺産分割協議)によって決めることになります。しかし、この遺産分割協議がまとまらず、家族間で争いになるケースは少なくありません。財産の大小にかかわらず、相続トラブルは起こり得ます。
遺言書を作成しておくことで、自分の意思に沿った財産の分配が可能になり、相続手続きにおける家族の負担を減らし、無用な争いを未然に防ぐことができます。
遺言書が残されている場合は、原則遺言書に記載されている内容に基づき、相続を行います。遺言書を作成しておくことで、自身の希望通りに財産を渡せる可能性が高まります。また、親族内での相続争いが起きにくくなります。
特に、法定相続人以外の人(お世話になった人など)に財産を遺したい場合や、相続人ごとに渡す財産を指定したい場合には、遺言書が不可欠です。また、2023年4月からの民法改正により、相続開始から10年が経過すると、原則として法定相続分で遺産分割を行うルールが導入され、早期の準備がより重要になっています。
遺言書の種類と選び方
遺言書には主に3つの種類があり、それぞれ作成方法や特徴が異なります。
- 自筆証書遺言:全文、日付、氏名を自筆で書き、押印して作成します。手軽で費用がかからない反面、形式に不備があると無効になるリスクがあります。法務局での保管制度を利用すると、検認が不要になるなどのメリットがあります。
- 公正証書遺言:公証役場で公証人に作成してもらう遺言書です。作成に費用と手間がかかりますが、専門家が関与するため形式不備で無効になる心配がなく、最も確実性の高い方法です。
- 秘密証書遺言:内容は秘密にしたまま、遺言書の存在だけを公証役場で証明してもらう形式です。内容は保護されますが、形式不備のリスクは残ります。
どの形式が良いかは状況によりますが、財産内容が複雑な場合や、確実に意思を実現したい場合は、専門家のアドバイスを受けながら公正証書遺言を作成することをおすすめします。
一人で悩まないで。終活の相談先
終活でやるべきことは多岐にわたるため、一人ですべてを進めるのは大変です。不安なことや分からないことがあれば、専門家や公的機関に相談しましょう。
- 市区町村の相談窓口・地域包括支援センター:介護や医療、生活全般に関する相談に無料で応じてくれます。
- 司法書士・行政書士:遺言書の作成や相続手続きの専門家です。
- 弁護士:相続トラブルが予想される場合など、法的な問題全般について相談できます。
- 税理士:相続税に関する相談ができます。
- 葬儀社・石材店:葬儀やお墓に関する具体的な相談ができます。
- 金融機関:信託銀行などが終活支援サービスを提供している場合があります。
初回相談は無料で行っている専門家も多いので、まずは気軽に問い合わせてみましょう。
まとめ:できることから一歩ずつ、未来の安心のために
終活は、決して後ろ向きな活動ではありません。自分の人生と向き合い、未来への準備をすることで、残りの人生を安心して、より自分らしく生きるための道しるべとなります。今回ご紹介した5つのステップを参考に、まずはエンディングノートを開くことから始めてみてはいかがでしょうか。
一度にすべてを完璧にやろうとせず、自分のペースで、できることから一歩ずつ進めていくことが大切です。あなたの終活が、あなた自身と、あなたの大切な家族にとって、未来の安心につながることを願っています。

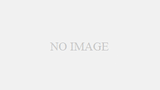
コメント