人生のエンディング、お金のことで不安になっていませんか?
終活に関するお得な情報や専門家からのアドバイスを受け取りたい方は、まずはこちらからLINE公式アカウントにご登録ください!
「人生100年時代」と言われる現代、多くの人が自らの人生の終わり方について考える「終活」に関心を持っています。しかし、いざ始めようとすると、多くの人が一つの大きな壁にぶつかります。それは、「一体、終活にはいくら準備すればいいのか、見当もつかない…」というお金の問題です。
インターネットで検索してみると、「終活にかかった費用は平均約503万円」という衝撃的なデータを見つけるかもしれません。一方で、別のサイトでは「費用の相場は80万~250万円」と書かれていたり、「80万円~600万円程度」とさらに幅の広い数字が示されていたりします。
「なぜこんなに金額が違うの?」「結局、自分にはいくら必要なの?」——そんな疑問と不安が頭をよぎるのも無理はありません。
ご安心ください。この記事を最後まで読めば、そのモヤモヤは晴れ渡ります。本記事では、終活の費用に関するあらゆる情報を網羅し、専門家の視点から徹底的に解説します。具体的には、以下のことが明確になります。
- なぜ終活費用に関する情報が錯綜しているのか、その理由がわかります。
- 葬儀やお墓から、生前整理、相続手続きまで、具体的な費用の内訳と相場がわかります。
- あなた自身の状況に合わせた「自分だけの終活予算」を立てる具体的な方法がわかります。
- 費用を賢く抑えるコツや、計画的に準備するためのノウハウがわかります。
この記事は、単なる費用の羅列ではありません。あなたが終活という旅を、お金の不安なく、自分らしく、そして前向きに進めるための「羅針盤」となることを目指しています。さあ、一緒に未来への安心を手に入れる第一歩を踏み出しましょう。
終活費用の全体像:平均は503万円?それとも80万円?
終活費用の話になると、まず目にするのが「平均額」です。しかし、前述の通り、その数字は情報源によって大きく異なります。この混乱の裏には、終活という言葉が持つ意味の広さがあります。ここでは、まず大きな視点から費用の全体像を捉え、なぜ金額に大きな幅が生まれるのかを解き明かしていきます。
2つの「平均費用」の正体:広義の終活 vs 狭義の終活
メディアや調査で目にする「平均費用」は、大きく分けて2つの異なる定義に基づいています。この違いを理解することが、混乱を解消する第一歩です。
広義の終活費用:平均約503万円の世界
「終活にかかった費用は平均約503万円」というデータは、株式会社ハルメクホールディングスが運営する「ハルメク 生きかた上手研究所」が2025年に発表した調査結果です。この調査では、50~79歳の男女2,016名を対象に、終活として実施した内容とその費用が尋ねられました。
この調査で費用が高額になった背景には、その内容にあります。費用が高かった項目の上位には、「投資信託、株式投資など資産運用をはじめる」「終のすみかとして、自宅をリフォーム」「不動産の整理・処分」といった項目が並びます。
つまり、この「503万円」という数字は、単に死後の備えだけでなく、「残りの人生をより豊かに、安心して過ごすための投資」まで含んだ、非常に広い意味での終活費用を反映しているのです。資産運用やリフォームは、必ずしも全員が行うものではなく、個人のライフプランに大きく左右されます。これを「広義の終活費用」と捉えることができます。
狭義の終活費用:80万円~250万円の世界
一方で、多くの終活情報サイトや専門家が語る「80万円~250万円」や「80万円~600万円」といった相場は、より直接的に「死」に関連する準備費用を指しています。これは「狭義の終活費用」と言えるでしょう。
具体的には、以下のような項目が中心となります。
- 葬儀・お墓に関する費用:葬儀の形式やお墓の種類によって変動します。
- 医療・介護に関する費用:晩年の医療費や介護サービスの自己負担分です。
- 生前整理に関する費用:遺品整理や自宅の片付けにかかる費用です。
- 相続・遺言に関する費用:遺言書の作成や相続手続きを専門家に依頼する費用です。
これらの項目は、多くの人にとって必要となる可能性が高いものであり、終活を考える上でベースとなる費用と言えます。こちらの相場の方が、より現実的な「最低限の備え」としてイメージしやすいかもしれません。
なぜ費用に数百万円もの幅が生まれるのか?
広義と狭義の違いを理解した上で、それでもなお「80万円~600万円」といった大きな価格差が存在するのはなぜでしょうか。その答えは、終活が極めて「個人的な活動」であるという事実にあります。費用を左右する主な要因は、以下の3つです。
- 個人の希望や価値観
人生の締めくくり方は人それぞれです。例えば葬儀一つとっても、「親しい家族だけで静かに見送られたい」と考える人もいれば、「多くの友人に囲まれて盛大に送り出してほしい」と願う人もいます。お墓についても、「先祖代々の墓に入りたい」「自然に還れる樹木葬がいい」「都心でアクセスの良い納骨堂がいい」など、希望は多岐にわたります。こうした希望の違いが、費用に直接反映されます。 - 現在の状況や資産
現時点での状況も費用を大きく変動させます。例えば、先祖代々のお墓があり、そこに入れるのであれば、新たにお墓を購入する数百万円の費用はかかりません。持ち家がある場合、その家をどうするのか(誰かが住み継ぐのか、売却するのか、解体するのか)によって、整理や処分の費用が大きく変わってきます。 - 家族構成や人間関係
頼れる家族や親族がいるかどうかも、費用に影響します。例えば、身の回りの整理を家族が手伝ってくれれば、専門業者に依頼する費用を抑えることができます。一方で、身元保証人がいない場合や、死後の事務手続きを頼める人がいない場合は、専門のサービスを利用する必要があり、その分の費用が発生します。矢野経済研究所の調査によれば、身元保証や生前整理といった終活関連ビジネスの市場は拡大傾向にあり、2025年度には257億円を超えると予測されています。これは、社会構造の変化に伴い、専門サービスへの需要が高まっていることを示しています。
重要なのは「自分にとって何が必要か」を知ること
ここまで見てきたように、「終活費用の平均」は、あくまで一つの参考値に過ぎません。503万円という数字に怯える必要も、80万円で足りると安心するのも早計です。
最も大切なのは、平均額に一喜一憂するのではなく、「自分自身の終活には、何が必要で、それぞれにいくらかかるのか」を具体的に把握することです。他人のものさしではなく、自分のものさしで予算を考える。それが、お金の不安を解消し、納得のいく終活を実現するための唯一の道です。
では、具体的にどのような項目があり、それぞれにどれくらいの費用がかかるのでしょうか。次の章では、終活費用を詳細な項目に分解し、一つひとつの相場を詳しく見ていきましょう。このパートが、あなたの「自分だけの予算」を立てるための基礎知識となります。
【項目別】終活費用の詳細な内訳と相場
この章では、終活にかかる費用を具体的な項目に分解し、それぞれの相場と内容を詳しく解説します。この記事の核となる部分ですので、ご自身の状況や希望と照らし合わせながら、じっくりと読み進めてください。費用は大きく4つのカテゴリーに分けて整理します。
カテゴリー1:「死後の備え」に関する費用
人生の最期を迎えた後、必ず必要となるのが葬儀やお墓です。これらは終活費用の中でも特に大きな割合を占める項目であり、選択によって費用が大きく変動します。
葬儀費用
葬儀の費用は、その形式や規模によって大きく異なります。近年では、従来の一般葬だけでなく、家族葬や一日葬、直葬(火葬式)など、多様な選択肢が生まれています。
株式会社鎌倉新書が2024年に実施した「第6回お葬式に関する全国調査」によると、葬儀の種類別の費用相場は以下のようになっています。
- 一般葬(平均 約161.3万円):家族や親族だけでなく、友人、知人、会社関係者など、生前お世話になった方々を広く招いて行う伝統的な形式の葬儀です。参列者が多いため、会場費や飲食費、返礼品費などが高くなる傾向があります。
- 家族葬(平均 約105.7万円):故人とごく親しい家族や親族、友人を中心に行う小規模な葬儀です。参列者が少ないため、一般葬に比べて費用を抑えることができます。内訳としては、葬儀一式費用が約72.0万円、飲食代が約17.1万円、返礼品が約16.5万円となっています。
- 一日葬:通夜を行わず、告別式と火葬を1日で行う形式です。通夜振る舞いなどの飲食費や、2日間にわたる会場使用料を削減できるため、家族葬よりもさらに費用を抑えられる場合があります。
- 直葬・火葬式(相場 20万円~50万円程度):通夜や告別式といった儀式を行わず、ごく限られた人数で火葬のみを行う最もシンプルな形式です。費用を大幅に抑えられる一方、お別れの時間が短くなる、菩提寺がある場合は納骨を断られる可能性があるなどの注意点もあります。
また、これらの費用に加えて、僧侶などにお渡しする「お布施」が必要になる場合があります。お布施は読経や戒名に対するお礼であり、決まった金額はありませんが、宗派や寺院との関係性によって数十万円単位で必要になることもあります。事前に確認しておくことが重要です。
お墓に関する費用
お墓もまた、終活における大きな費用項目です。先祖代々のお墓があれば費用は抑えられますが、新たに購入する場合は数百万円単位の出費となることも珍しくありません。近年では、ライフスタイルの変化に伴い、お墓の形態も多様化しています。
主な種類と費用相場は以下の通りです。
- 一般墓(相場 100万~400万円):墓石を建立する伝統的なお墓です。費用は墓石代と永代使用料(土地を使用する権利)で構成され、都市部ほど高額になる傾向があります。これに加えて、年間5,000円~15,000円程度の管理費が別途必要になります。
- 納骨堂(相場 50万~100万円):屋内の施設に遺骨を安置するタイプのお墓です。ロッカー式、仏壇式、自動搬送式など様々な形態があります。天候に左右されずお参りできる、比較的費用が安いといったメリットがあります。
- 樹木葬(相場 5万~80万円):墓石の代わりに樹木をシンボルとするお墓です。遺骨の埋葬方法によって費用が異なり、他の人と一緒に埋葬される合祀型(5万~20万円)、個別に埋葬される個人型(15万~60万円)、家族単位で利用できる家族型(20万~80万円)などがあります。
- 永代供養墓(相場 3万~):お墓の承継者がいない場合でも、寺院や霊園が永代にわたって遺骨を管理・供養してくれるお墓です。他の人の遺骨と一緒に埋葬される合祀墓が最も安価で、3万円程度から見つけることも可能です。個別で安置するタイプもありますが、一定期間が過ぎると合祀されるのが一般的です。
また、既にあるお墓を撤去して更地に戻す「墓じまい」にも費用がかかります。お布施、石材店の工事費、離檀料などを合わせると、数十万円程度かかる場合があります。
カテゴリー2:「生前の整理」に関する費用
残された家族に負担をかけないために、元気なうちから身の回りを整理しておくことも重要です。物だけでなく、デジタル資産の整理も現代ならではの課題です。
遺品整理・生前整理
自宅にある家財や思い出の品々を整理します。自分で行うか、専門業者に依頼するかで費用が大きく変わります。
- 自分でやる場合(相場 3万~10万円):主な費用は、不用品の処分料(粗大ごみ処理手数料など)、清掃用具代、荷物を運ぶためのレンタカー代などです。時間と労力はかかりますが、費用を最も安く抑えることができます。
- 業者に依頼する場合(相場 数万~60万円):物の量や部屋の間取り、作業内容によって費用が変動します。例えば、1LDKで7万円~、3LDKで17万円~といった料金設定が一般的です。不用品の買取サービスを行っている業者を選べば、費用を相殺することも可能です。
特に、実家などが「空き家」になる場合は注意が必要です。空き家の整理・処分には、解体費用や家財道具の処分費用、不動産売却に伴う仲介手数料などが発生し、平均で約110万円ほどかかるとされています。
デジタル終活
パソコンやスマートフォンの中のデータ、SNSアカウント、ネット銀行やネット証券の口座など、デジタル資産の整理も現代の終活には欠かせません。
- 自分でやる場合(費用 0円):IDやパスワード、解約してほしいサービスなどをリスト化し、エンディングノートなどにまとめておけば費用はかかりません。
- 業者に依頼する場合(相場 5,000円~10万円):デジタル遺品の整理サービスを提供する専門業者に依頼する場合の費用です。データのバックアップや消去、各種アカウントの解約代行など、サービス内容は多岐にわたります。
カテゴリー3:「医療・介護」に関する費用
高齢期になると、医療や介護が必要になる可能性が高まります。これらの費用は公的保険で大部分がカバーされますが、自己負担分も考慮しておく必要があります。
医療・介護費用の目安
老後の医療費や介護費用として、最低でも100万円程度は備えておきたいと言われています。ただし、これはあくまで目安であり、個人の健康状態や希望する介護の形によって大きく変動します。
- 医療費:日本の公的医療保険制度には「高額療養費制度」があり、1ヶ月の医療費の自己負担額には上限が設けられています。そのため、医療費が青天井に増え続けることはありません。しかし、保険適用外の治療(先進医療など)や、差額ベッド代、入院中の食事代などは自己負担となります。
- 介護費用:介護が必要になった場合、在宅でサービスを受けるか、施設に入居するかで費用が大きく異なります。在宅介護は費用を抑えられますが、家族の負担が大きくなります。介護施設に入居する場合、施設の種類(特別養護老人ホームなどの公的施設か、有料老人ホームなどの民間施設か)や要介護度によって費用は様々ですが、月々10万円~20万円程度の費用がかかるのが一般的です。
これらの費用は、いつ、どのくらいの期間必要になるか予測が難しいため、預貯金だけでなく、民間の医療保険や介護保険で備えておくことも有効な選択肢となります。
カテゴリー4:「意思と財産」を伝えるための費用
自分の意思を家族に伝え、大切な財産を円滑に引き継いでもらうための準備にも、費用がかかる場合があります。ただし、やり方次第で費用を大きく抑えることも可能です。
エンディングノート
自分の情報や希望、家族へのメッセージなどを書き記しておくノートです。法的効力はありませんが、家族が手続きを進める上で非常に役立ちます。
- 費用:0円~数千円程度
- 市販のエンディングノートは1,000円前後で購入できます。また、インターネットで無料のテンプレートをダウンロードしたり、普通の大学ノートに書き記したりすれば、費用はほとんどかかりません。
- 専門家に作成支援を依頼する場合は、数万円~10万円程度の費用がかかることもあります。
遺言書作成
財産の分け方などについて法的な効力を持たせたい場合は、遺言書の作成が必要です。主に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類があります。
- 自筆証書遺言(費用:ほぼ0円):全文を自分で手書きする遺言書です。費用は紙とペン代くらいで済みますが、法律で定められた形式を守らないと無効になるリスクがあります。
- 公正証書遺言(費用:数万円~):公証役場で公証人に作成してもらう遺言書です。原本が公証役場に保管されるため、紛失や改ざんの心配がなく、最も確実な方法です。費用は財産の価額に応じて変動しますが、数万円から十数万円が一般的です。
- 専門家への依頼費用(相場 10万円~30万円):弁護士、司法書士、行政書士などに遺言書の作成を依頼した場合の費用です。専門家が関与することで、法的に有効で、かつ内容に不備のない遺言書を作成できます。
相続手続きに関する費用
遺された家族が相続手続きを行う際にも、専門家への依頼費用が発生することがあります。これも見越して準備しておくと、より安心です。
- 相続税申告の税理士費用(遺産総額の0.5~1.0%が目安):相続財産が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合、相続税の申告が必要です。この申告を税理士に依頼する場合、報酬は遺産総額の0.5%~1.0%が相場とされています。例えば、遺産総額が5,000万円なら、25万円~50万円が目安となります。
- 不動産の相続登記の司法書士費用:不動産を相続した場合、名義変更(相続登記)が必要です。これを司法書士に依頼する場合、数万円~十数万円の費用がかかります。
キーポイント:費用の全体像
終活費用は、大きく4つのカテゴリーに分けられます。それぞれの項目で、自分の希望や状況に合わせて「必要か、不要か」「どのくらいのレベルを望むか」を考えることが、予算作成の第一歩です。
【実践編】自分だけの終活予算を立てる3ステップ
前章で終活費用の内訳と相場を学びました。ここからは、その知識を元に、あなただけのオリジナルな終活予算を立てるための具体的な手順を3つのステップで解説します。この作業を通じて、漠然としたお金の不安が、具体的な目標へと変わっていきます。
ステップ1:現状を把握する(リストアップ)
予算を立てる最初のステップは、自分の現在地を知ることです。つまり、自分が今どれくらいの資産と負債を持っているのかを正確に把握することから始めます。
資産の棚卸し
まずは、プラスの財産をすべてリストアップします。エンディングノートや普通のノートに書き出していくと良いでしょう。主な項目は以下の通りです。
- 預貯金:普通預金、定期預金など。銀行名、支店名、口座番号、おおよその残高を記載します。
- 不動産:土地、建物(自宅、マンション、アパートなど)。所在地、名義、おおよその評価額(固定資産税評価額など)を調べます。
- 有価証券:株式、投資信託、国債など。証券会社名、銘柄、数量、おおよその時価を記載します。
- 生命保険:死亡保険金、医療保険、個人年金保険など。保険会社名、証券番号、受取人、保障内容をまとめます。
- その他:自動車、貴金属、骨董品、ゴルフ会員権など、財産的価値のあるものをリストアップします。
負債の確認
次に、マイナスの財産、つまり負債をリストアップします。これも相続の対象となるため、正確に把握しておくことが重要です。
- ローン:住宅ローン、自動車ローン、カードローンなど。借入先、現在の残高、返済計画を記載します。
- 借入金:個人からの借金など。
- 未払金:税金、公共料金、クレジットカードの未払い分など。
この作業は少し手間がかかるかもしれませんが、自分の経済状況を客観的に見つめ直す良い機会になります。また、このリストはそのまま家族への引き継ぎ資料としても活用できます。
ステップ2:希望を整理する(やりたいことリスト)
現状を把握したら、次は未来に目を向けます。「自分はどのような最期を迎えたいのか」「残りの人生で何をしたいのか」という希望を具体的にしていきます。
第2章で解説した項目を参考に、一つひとつ自分に問いかけてみましょう。
- 葬儀:「家族だけでこぢんまりと、家族葬で送ってほしい。宗教的な儀式は不要で、無宗教形式がいいな。」
- お墓:「子どもに負担をかけたくないから、承継者のいらない永代供養墓にしたい。できれば、桜の木の下で眠れる樹木葬がいい。」
- 生前整理:「元気なうちに、クローゼットの中身を半分に減らそう。写真はデータ化して、アルバムは1冊にまとめたい。」
- 医療・介護:「もし介護が必要になったら、住み慣れた自宅で過ごしたい。でも、家族に迷惑がかかるなら、評判の良いあの介護付き有料老人ホームに入りたい。」
- 財産:「自宅は妻に、預貯金は子どもたちに平等に分けたい。その意思を明確にするために、公正証書遺言を作成しておこう。」
この時、終活を「死への準備」とだけ捉えるのではなく、「これからの人生をどう楽しむか」という視点も加えることが大切です。例えば、「夫婦でヨーロッパ旅行に行きたい」「孫の大学入学祝いに100万円を贈りたい」といった「やりたいことリスト」も一緒に作成することで、終活がより前向きで、生きる希望に満ちた活動になります。
ステップ3:費用を計算し、資金計画を立てる
現状把握と希望の整理ができたら、いよいよ最終ステップです。ステップ2で作成した「やりたいことリスト」に、第2章で学んだ費用相場を当てはめて、あなただけの終活予算を算出します。
終活費用シミュレーションシート(例)
以下のような簡易的なシートを作成し、概算費用を計算してみましょう。
| カテゴリー | 項目 | 自分の希望 | 費用目安 |
|---|---|---|---|
| 死後の備え | 葬儀 | 家族葬(参列者20名程度) | 1,050,000円 |
| お墓 | 樹木葬(個人型) | 500,000円 | |
| 生前の整理 | 生前整理 | 自分で実施+一部業者依頼 | 150,000円 |
| デジタル終活 | 自分で実施 | 0円 | |
| 医療・介護 | 医療・介護への備え | 当面の自己負担分として | 1,000,000円 |
| 意思と財産 | 遺言書作成 | 公正証書遺言を司法書士に依頼 | 150,000円 |
| 相続手続き | 家族への予備費として | 200,000円 | |
| 終活費用の合計(A) | 3,050,000円 | ||
資金計画の立案
算出した終活費用の合計額(A)と、ステップ1で把握した資産額を比較します。
現在の資産合計(B) – 終活費用の合計(A) = 残りの生活資金・予備費
この計算結果によって、今後の資金計画が見えてきます。
- 資金に余裕がある場合:安心材料になります。やりたいことリストの希望をグレードアップしたり、生前贈与を検討したりと、より積極的なプランニングが可能です。
- 資金がギリギリ、または不足する場合:不安になる必要はありません。課題が明確になったことは大きな前進です。次の章で解説する「費用を抑えるコツ」や「費用を準備する方法」を参考に、具体的な対策を立てていきましょう。
このように、3つのステップを踏むことで、漠然としていた「終活費用」が、具体的な数字と計画に落とし込まれます。これが、お金の不安から解放されるための最も確実な方法です。
賢く備える!終活費用を抑える・準備する方法
予算計画を立てた結果、「思ったより費用がかかるな」「少しでも安く抑えたい」「資金が足りない分はどう準備しよう」といった新たな課題が見えてきた方もいるでしょう。この章では、そんなニーズに応えるための具体的なノウハウを、「費用を抑えるコツ」と「費用を準備する方法」の2つの側面から解説します。
今すぐできる!終活費用を抑える5つのコツ
少しの工夫や見直しで、終活費用は大きく削減できる可能性があります。賢く費用を抑えるための5つのポイントをご紹介します。
- 葬儀・お墓の規模や形式を見直す
費用が最も大きい葬儀やお墓は、見直しの効果も絶大です。例えば、一般葬から家族葬へ規模を縮小するだけで、数十万円の節約に繋がります。お墓も、一般墓にこだわらず、永代供養墓や樹木葬を選択肢に入れることで、費用を1/10以下に抑えることも可能です。大切なのは世間体ではなく、自分や家族が納得できる形を選ぶことです。 - 生前整理を徹底し、不用品は売却する
元気なうちに自分で不用品を整理・処分すれば、業者に依頼する遺品整理費用を大幅に削減できます。衣類や本、家具などはリサイクルショップやフリマアプリで売却すれば、逆にお金になることもあります。残すものを厳選し、家族が整理しやすいようにラベリングしておくだけでも、遺族の負担は大きく軽減されます。 - 専門家への依頼範囲を限定する
専門家の力は必要ですが、すべてを丸投げすると費用がかさみます。例えば、遺言書は専門家のアドバイスを受けながらも、最終的には費用のかからない「自筆証書遺言」で作成するという選択肢もあります。相続手続きなども、自分でできる部分は自分で行い、複雑な部分だけを専門家に依頼することで、費用をコントロールできます。 - 公的制度を最大限に活用する
あまり知られていませんが、終活に関連する費用を補助してくれる公的制度があります。- 葬祭費・埋葬料:国民健康保険や社会保険の加入者が亡くなった場合、葬儀を行った人(喪主など)に数万円(自治体や組合によるが5万円前後が多い)が支給されます。申請しないと受け取れないため、忘れずに手続きしましょう。
- 高額療養費制度:前述の通り、医療費の自己負担額を一定に抑える制度です。事前に「限度額適用認定証」を入手しておくと、窓口での支払いが自己負担限度額までで済みます。
これらの制度を上手に活用することで、実質的な負担を軽減できます。
- 相見積もりを徹底する
葬儀社や遺品整理業者、石材店などを利用する際は、必ず複数の業者から見積もり(相見積もり)を取りましょう。同じ内容でも業者によって料金体系は大きく異なります。料金だけでなく、サービス内容や担当者の対応などを比較検討することで、納得のいく業者を適正価格で選ぶことができます。
計画的に進める!終活費用を準備する4つの方法
費用を抑える努力と並行して、必要な資金を計画的に準備していくことも大切です。ここでは、代表的な4つの準備方法をご紹介します。
- 保険の活用(見直し・新規加入)
生命保険は、終活費用を準備する上で非常に有効な手段です。死亡保険金は、受取人固有の財産となるため、相続手続きを待たずに現金を受け取ることができ、葬儀費用などの支払いに充てやすいという大きなメリットがあります。- 終身保険:保障が一生涯続くため、確実に死亡保険金を受け取れます。
- 葬儀保険(少額短期保険):葬儀費用など、使途を限定した少額の保障を割安な保険料で準備できます。高齢でも加入しやすい商品が多いのが特徴です。
現在加入している保険の内容を確認し、目的に合っているか見直すことから始めましょう。
- 計画的な貯蓄・資産運用
終活費用は、ある程度まとまった金額になるため、計画的な貯蓄が基本です。それに加えて、長期的な視点で資産を育てる「資産運用」も選択肢の一つです。- つみたてNISA:少額からの長期・積立・分散投資を支援するための非課税制度。得られた利益が非課税になります。
- iDeCo(個人型確定拠出年金):自分で掛金を拠出し運用する私的年金制度。掛金が全額所得控除になるなど、税制上の優遇が大きいのが特徴です。
これらは老後資金準備の一環として、終活費用の準備にも繋がります。ただし、元本保証ではないため、リスクを理解した上で利用することが重要です。
- 生前贈与の活用(相続税対策)
相続税がかかる可能性のある方は、生前に財産を贈与しておくことで、将来の相続税負担を軽減できる場合があります。- 暦年贈与:1人あたり年間110万円までの贈与であれば、贈与税がかかりません。この非課税枠を利用して、毎年少しずつ子どもや孫に資金を渡していく方法です。
- お墓や仏壇の生前購入:お墓や仏壇、仏具などは、生前に購入して支払いを済ませておくと、相続税の課税対象から外れます。相続財産を非課税財産に変えることで、節税に繋がります。
ただし、税制は複雑で改正も頻繁に行われるため、実行する際は税理士などの専門家に相談することをお勧めします。
- 不動産の活用(リースバック)
「まとまった資金は必要だが、住み慣れた家は離れたくない」という場合に有効なのが「リースバック」です。自宅を不動産会社などに売却して現金化し、同時にその会社と賃貸契約を結ぶことで、売却後も家賃を払いながら同じ家に住み続けられる仕組みです。老後の生活資金や終活費用を確保しつつ、生活環境を変えずに済むというメリットがあります。
ひとりで悩まない!終活の費用に関する悩み別相談先リスト
終活の費用計画は、自分一人で抱え込むには複雑で難しい問題も多く含まれます。そんな時は、専門家の力を借りるのが賢明です。ここでは、具体的な悩みに応じて、どこに何を相談すれば良いのかをまとめた相談先リストをご紹介します。相談へのハードルを下げ、最初の一歩を踏み出すきっかけにしてください。
お金の計画全般(ライフプラン)について相談したい
「終活費用も含めて、老後全体の資金計画を立てたい」「今の資産で将来の生活は大丈夫か診断してほしい」といった、お金に関する総合的な相談に適した窓口です。
- FP(ファイナンシャルプランナー)
お金の専門家であるFPは、家計や資産状況を分析し、終活費用、老後資金、保険の見直しなど、生涯にわたる資金計画(ライフプラン)の作成をサポートしてくれます。中立的な立場でアドバイスをくれるのが強みです。
費用目安:相談料は、無料のところから、1時間あたり5,000円~1万円程度の有料のところまで様々です。 - 銀行の相談窓口
多くの銀行では、終活や相続に関する専門の相談窓口やスタッフを配置しています。資産運用や遺言信託、保険商品など、その銀行が取り扱う金融商品と絡めた提案を受けられるのが特徴です。
費用目安:相談自体は無料の場合がほとんどです。
遺言・相続の法的手続きについて相談したい
「法的に有効な遺言書を作成したい」「相続で家族が揉めないように対策したい」「任意後見や家族信託について知りたい」といった、法律が関わる専門的な相談先です。
弁護士、司法書士、行政書士が主な相談先となりますが、それぞれ対応できる業務範囲が異なります。
- 弁護士
法律の専門家として、遺言書作成から相続トラブルの代理交渉まで、相続に関するあらゆる法律問題に対応できます。将来的に紛争が予想される場合に最も頼りになります。
費用目安:相談料は30分5,000円~1万円程度。遺言書作成の依頼は10万円~30万円程度が相場です。 - 司法書士
登記の専門家であり、遺言書作成の支援や、相続発生後の不動産の名義変更(相続登記)手続きを得意とします。任意後見や家族信託に関する手続きも依頼できます。
費用目安:弁護士と比較すると、費用はやや安価な傾向があります。遺言書作成は10万円~30万円程度が目安です。 - 行政書士
官公署に提出する書類作成の専門家です。遺言書の作成支援や、遺産分割協議書の作成など、紛争性のない書類作成業務を中心に行います。
費用目安:司法書士と同様、弁護士よりは安価な傾向があります。遺言書作成は10万円~30万円程度が目安です。
相続税について相談したい
「自分の財産だと相続税はかかるのか知りたい」「効果的な相続税対策を教えてほしい」といった、税金に関する相談は税理士の専門分野です。
- 税理士
税の専門家として、相続税額のシミュレーション、生前贈与などを活用した節税対策の提案、相続発生後の相続税申告書の作成・提出などを行います。
費用目安:相続税申告の依頼費用は、遺産総額の0.5%~1.0%が相場です。生前の節税対策の相談は10万円~30万円程度が目安となります。
どこに相談していいかわからない場合
「何から手をつけていいかわからない」「まずは気軽に話を聞いてみたい」という方は、公的な窓口や民間の総合サービスを利用するのがお勧めです。
- 自治体の終活相談窓口
多くの市区町村では、福祉課や高齢者支援課などで、無料または低額の終活相談会を実施しています。例えば、東京都豊島区には「終活あんしんセンター」が設置されており、終活全般の相談が可能です。お住まいの自治体のホームページなどで確認してみましょう。 - 終活サポートサービスを提供している民間企業
葬儀社や石材店、信託銀行、NPO法人などが、終活に関する様々なサービスをワンストップで提供しています。身元保証や死後事務委任、各種専門家の紹介など、幅広いニーズに対応してくれます。月額数百円から相談できるサービスもあります。
キーポイント:相談は早めに
専門家への相談は、問題が複雑化する前に、早めに行うことが重要です。多くの専門家が無料相談を実施しています。まずは無料相談を活用して、信頼できる専門家を見つけることから始めてみましょう。
まとめ:終活は未来への安心を手に入れるための投資
この記事では、終活にかかる費用について、その全体像から詳細な内訳、具体的な予算の立て方、そして費用を賢く準備・節約する方法まで、多角的に解説してきました。
最後に、本記事の重要なポイントを振り返ります。
- 終活費用は「平均503万円」という広義の数字と、「80万円~」という狭義の数字が存在しますが、最も重要なのは「人それぞれ」であるということ。平均額に惑わされず、「自分に必要な費用」を知ることがスタートラインです。
- 費用は大きく「①死後の備え(葬儀・お墓)」「②生前の整理」「③医療・介護」「④意思と財産(遺言・相続)」の4つに大別できます。
- 「①現状把握 → ②希望整理 → ③費用計算」という3つのステップを踏むことで、漠然とした不安を具体的な「自分だけの予算」に変えることができます。
- 葬儀の規模を見直したり、公的制度を活用したりと、費用を賢く抑える工夫はたくさんあります。また、保険や貯蓄、生前贈与など、計画的に費用を準備する方法も多様です。
- 一人で悩まず、FPや弁護士、自治体の窓口など、悩みに応じて専門家や相談窓口を活用することが、問題をスムーズに解決する鍵となります。
終活は、決して「死への準備」というネガティブな活動ではありません。むしろ、お金の不安を解消し、残された家族への負担を軽くすることで、「残りの人生を安心して、より自分らしく、豊かに生きるための前向きな活動」です。それは、未来の自分と大切な家族への、最高の「投資」と言えるでしょう。
この記事が、あなたの終活という旅の、頼れる地図となることを心から願っています。まずはエンディングノートを開き、自分の考えを書き出してみるなど、今日からできる小さな一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。
終活の第一歩、踏み出せそうでしょうか?
さらに詳しい情報や、専門家による個別相談会のお知らせなど、あなたの終活をサポートする情報をLINEでお届けしています。ぜひご登録いただき、あなたの「これから」にお役立てください。

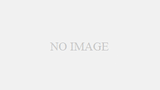
コメント