富士山だけじゃない、富士市の奥深い歴史
静岡県富士市と聞けば、多くの人が雄大な富士山の姿を思い浮かべるでしょう。しかし、この街の魅力はそれだけではありません。富士山の麓に広がるこの地は、縄文時代から人々が暮らし、古代には強大な王が君臨し、中世には歴史を揺るがす合戦の舞台となりました。そして江戸時代には、東海道の要衝として、また富士川の激しい流れと共存する人々の知恵と努力の証として、数多くの物語が刻まれてきました。
この記事では、富士山の絶景の裏に隠された、富士市の豊かな歴史を体感できる10の観光スポットを厳選してご紹介します。古墳、古戦場、文化財建築、そして人々の信仰の跡を巡る旅へ、あなたをご案内します。
時代を巡る、富士市の歴史観光スポット10選
古代から近代まで、様々な時代の息吹を感じられるスポットを巡り、富士市の歴史の深さに触れてみましょう。
1. 浅間古墳 – 駿河の王が眠る古代のモニュメント
富士市の歴史探訪は、まず古代のロマンを感じる場所から始めましょう。浅間古墳(せんげんこふん)は、4世紀中頃に築かれたとされる、東海地方最大級の前方後方墳です。全長約91メートルにも及ぶこの巨大な古墳は、当時の駿河国を治めた王の墓と推定されています。発掘調査は行われていませんが、その壮大な姿は、浮島ヶ原や駿河湾からよく見えるように計画的に造られており、古代におけるこの地の権力者の強大さを物語っています。。国の史跡にも指定されており、古代史ファンならずとも訪れたいパワースポットです。
2. 呼子坂・平家越 – 源平合戦の舞台を歩く
1180年、歴史上名高い富士川の戦いがこの地で繰り広げられました。平家の大軍に対し、源頼朝率いる源氏軍が陣を敷いたのが呼子坂(よぶこざか)周辺の高台です。ここで呼子を吹いて軍勢を集めたことが、その名の由来とされています。。一方、平家軍は戦わずして敗走したと言われています。その伝説を今に伝えるのが平家越(へいけごえ)の碑です。水鳥の羽音を源氏軍の夜襲と勘違いしたという逸話はあまりにも有名ですが、この地を歩けば、800年以上前の武士たちの緊張感が伝わってくるようです。
3. 山部赤人万葉歌碑 – 万葉集に詠われた絶景の地
「田子の浦ゆ うち出でてみれば 真白にぞ 富士の高嶺に 雪は降りける」—この有名な和歌を詠んだのは、奈良時代の歌人、山部赤人です。その舞台となった田子の浦の絶景を今に伝えるのが、ふじのくに田子の浦みなと公園内にある山部赤人万葉歌碑です。この歌碑は、地元の松野石で作られた8本の石柱に、万葉仮名で歌が刻まれており、富士山をかたどって配置されています。。古代の歌人が見たであろう富士山の雄大な姿に思いを馳せながら、美しい歌碑を眺める時間は、まさに至福のひとときです。
4. 雁堤 – 富士川の治水と人々の願いが刻まれた遺産
江戸時代、富士川はたびたび氾濫し、人々の暮らしを脅かしていました。この水害から加島平野を守るために築かれたのが、巨大な堤防である雁堤(かりがねづつみ)です。空から見ると雁が連なって飛ぶ姿に似ていることからその名が付きました。50年以上もかかった難工事であったため、工事の成功を祈って人身御供を行う「人柱伝説」も生まれました。。堤の南東角にある護所神社には、その人柱を供養する塔と碑が建てられており、治水という大事業に込められた先人たちの苦労と強い願いを今に伝えています。
5. 小休本陣常盤邸 – 東海道の賑わいを今に伝える武家屋敷
江戸時代、富士市岩淵地区は東海道と身延道が交差する交通の要衝「間宿(あいのしゅく)」として栄えました。その中心的な役割を担ったのが小休本陣常盤邸(こやすみほんじんときわてい)です。大名などの賓客が休憩に利用した格式高い建物で、現存する主屋は安政東海大地震(1854年)の後に再建されたものです。。格式を示す薬医門や、賓客が座った「上段の間」などが残されており、往時の賑わいと武家屋敷の様式を肌で感じることができます。国登録有形文化財にも指定されている貴重な歴史的建造物です。
6. 旧東泉院宝蔵 – 富士山信仰の歴史を秘めた宝物殿
現在の吉原公園には、戦国時代から明治初期まで富士山東泉院という有力な寺院が存在しました。この寺院は富士山修験道に関わる重要な拠点で、地域の神社を管理するほどの力を持っていました。。その東泉院唯一の遺構が、安政4年(1857年)に建てられた土蔵造りの旧東泉院宝蔵(きゅうとうせんいんほうぞう)です。内部は一般公開されており、江戸幕府からの朱印状や富士山の縁起絵図などが展示され、富士山信仰の奥深い歴史に触れることができます。国登録有形文化財(建造物)に指定されています。
7. 旧加藤酒店 – 昭和レトロを体感、文化財が生まれ変わった空間
歴史は博物館の中だけにあるのではありません。JR富士駅前の商店街に佇む旧加藤酒店は、1931年(昭和6年)に建てられた店舗兼住宅です。製紙業で栄えた当時の富士市の隆盛を物語るモダンな町家建築で、国登録有形文化財に指定されています。。この歴史ある建物は、約20年の時を経て、現在はダイニングバー「BAR×KAPPOU みかん」として再生。当時の趣を残した内装で、お酒や食事を楽しむことができます。歴史的建造物を活用したまちづくりの好例として、新しい観光の形を提案してくれるスポットです。
8. 米之宮浅間神社 – 富士山信仰と地域の暮らしを支えた古社
富士山信仰の中心である浅間神社。富士市にある米之宮浅間神社(よねのみやせんげんじんじゃ)は、653年以前の創建と伝わる歴史ある神社です。古くは米粒を御神体とし、人々に米食の福を与え恵む神として「米之宮」と称されました。。鮮やかな朱色の社殿が美しく、晴れた日には社殿の向こうに富士山を望むことができる絶景スポットとしても人気です。古くから地域の人々の暮らしと信仰の中心であり続けてきた、穏やかで清らかな空気が流れる場所です。
9. 天間沢遺跡 – 縄文時代に遡る、富士市最古の暮らしの痕跡
富士市の歴史は、古墳時代よりもさらに古く、縄文時代まで遡ります。それを証明するのが天間沢遺跡(てんまざわいせき)です。縄文時代中期(約5000~4000年前)の集落跡で、出土品の量や遺跡の規模ともに市内最大級を誇ります。。現在は天間沢遺跡公園として整備されており、当時の人々の暮らしに思いを馳せることができます。派手さはありませんが、この地に数千年前から続く人々の営みの原点に触れることができる、非常に貴重な場所です。
10. 松尾芭蕉の句碑 – 俳聖が富士の雪を詠んだ場所
江戸時代の俳聖・松尾芭蕉もまた、旅の途中でこの地を訪れました。JR富士駅近くには、芭蕉が詠んだとされる句を刻んだ松尾芭蕉の句碑があります。句は「ひと尾根は しくるゝ雲か 不二の雪」。貞享4年(1687年)の旅の途中で詠まれたと伝えられています。。日本を代表する文化人が、この地で富士山をどのように眺め、何を感じたのか。小さな句碑の前に立つと、時を超えて芭蕉の感性に触れられるような、不思議な感覚を味わうことができます。
おわりに:歴史を知れば、富士市の旅はもっと楽しくなる
今回ご紹介した10のスポットは、富士市が持つ豊かな歴史のほんの一部に過ぎません。市内には、今回紹介しきれなかった古墳群や史跡が数多く点在しています。富士市ウェブサイトによると、市内には約800基もの古墳があると言われています。
雄大な富士山を眺めながら、その麓で繰り広げられてきた人々の営みや歴史の物語に思いを馳せてみませんか。歴史というフィルターを通して街を歩けば、普段見ている景色がまったく違うものに見えてくるはずです。次の休日は、ぜひ富士市で奥深い歴史を巡る旅をお楽しみください。
記事制作・Webマーケティングのご相談は合同会社KUREBAへ
合同会社KUREBAでは、静岡県三島市を拠点に、本記事のようなSEOに強いコンテンツ制作、LINE公式アカウントの戦略的運用、効果的なホームページ制作サービスを提供しております。
貴社のビジネスの魅力を最大限に引き出し、ターゲット顧客に届けるための最適なソリューションをご提案します。Web集客や情報発信でお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

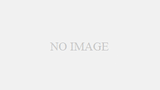
コメント