南海トラフ巨大地震をはじめ、台風による洪水や土砂災害など、様々な自然災害のリスクに備える必要がある静岡市。マイホームは一生に一度の大きな買い物だからこそ、「安心・安全」は最も重要な要素です。
しかし、具体的にどのような点に注意して住まいを選べば良いのでしょうか?
本記事では、静岡市で災害に強い家を選ぶための8つの重要ポイントを、公的データや専門情報を基に徹底解説します。土地選びから建物の性能、そして日々の備えまで、あなたの家族と資産を守るための知識を身につけましょう。
1. 静岡市が抱える災害リスクを正しく理解する
効果的な対策の第一歩は、住む場所のリスクを正確に知ることです。静岡市は、主に「地震・津波」「洪水」「土砂災害」という3つの大きなリスクを抱えています。
地震・津波のリスク
静岡市が最も警戒すべきは、南海トラフ巨大地震です。静岡県の第4次地震被害想定によると、最大クラスの地震が発生した場合、静岡市沿岸部には最大11m(平均6m)の津波が到達すると想定されています。また、過去には1935年や1965年に静岡市周辺でM6クラスの被害地震が発生しており、直下型地震への備えも不可欠です。
洪水(河川氾濫)のリスク
静岡市には安倍川や巴川といった主要な河川が流れており、台風や集中豪雨による洪水リスクが存在します。特に記憶に新しい令和4年(2022年)の台風15号では、巴川流域を中心に甚大な浸水被害が発生しました。市の洪水ハザードマップは、これらの河川が氾濫した場合の浸水想定区域を示しており、家選びの際には必ず確認すべき情報です。
土砂災害のリスク
静岡市は山間部も多く、がけ崩れ、土石流、地すべりといった土砂災害のリスクも軽視できません。静岡県は土砂災害防止法に基づき、危険度に応じて「土砂災害警戒区域(イエローゾーン)」と「土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)」を指定しています。レッドゾーンでは建築物の構造規制がかかるなど、土地利用に大きな制限があるため、特に注意が必要です。
2. ハザードマップで土地の安全性を「見える化」する
前述した災害リスクは、自治体が公表している「ハザードマップ」で具体的に確認できます。これは、安全な住まい選びにおける最も基本的かつ重要なツールです。
静岡市では、災害種別に応じた複数のハザードマップを整備・公開しています。これらを活用し、検討している土地や物件がどのようなリスクを抱えているのかを事前に把握しましょう。
- 静岡市防災マップ(地震・津波・土砂災害): 地震の揺れやすさ、津波浸水想定区域、土砂災害危険箇所などを一枚にまとめた総合的なマップです。冊子版のほか、Web上で詳細を確認できる「しずマップ」が便利です。
- 洪水ハザードマップ: 安倍川や巴川など、主要河川の氾濫による浸水想定区域や浸水深を示しています。避難所の場所も明記されています。
- 重ねるハザードマップ: 国土交通省が提供するWebサイトで、洪水、土砂災害、津波などのリスク情報を全国どこでも地図に重ねて表示できます。複数のリスクを一度に確認したい場合に非常に有効です。
これらのマップを使い、浸水想定区域や土砂災害警戒区域に含まれていないか、津波のリスクはどの程度かを確認することが、安全な土地選びの第一歩となります。
3. 地盤の強さを評価し、揺れにくい土地を選ぶ
同じ震度の地震でも、地盤の固さによって揺れの大きさは大きく異なります。一般的に、山を切り開いた造成地や、かつて川や沼地だった埋立地は地盤が軟弱な傾向にあり、地震の揺れが増幅されやすいとされています。一方で、台地や丘陵地などの固い地盤は揺れにくいです。
土地を購入して新築する場合は、必ず地盤調査を実施しましょう。調査の結果、地盤が弱いと判断された場合は、地盤改良工事が必要となります。コストはかかりますが、家の土台となる部分の安全性を確保するためには不可欠な投資です。中古物件を検討する際も、可能であれば地盤調査の履歴を確認することをおすすめします。
4. 建物の「構造強度」を見極める
土地の安全性を確認したら、次は建物そのものの強さに目を向けます。特に地震に対する強さは、静岡市で家を持つ上で最も重要な性能の一つです。
最重要指標「耐震等級」をチェック
建物の地震への強さを示す客観的な指標が「耐震等級」です。これは国の基準で3段階に分かれており、数字が大きいほど耐震性が高くなります。
- 耐震等級1: 建築基準法で定められた最低限の耐震性能。震度6強~7の地震で倒壊・崩壊しないレベル。
- 耐震等級2: 等級1の1.25倍の強度。学校や病院などの避難所に求められるレベル。
- 耐震等級3: 等級1の1.5倍の強度。消防署や警察署など、災害時の防災拠点となる建物と同等の最高レベル。
静岡市のように大規模地震のリスクが高い地域では、「耐震等級3」を取得していることが、安心して暮らすための強力な条件となります。新築時はもちろん、中古物件でも耐震等級は必ず確認しましょう。
「制震」「免震」という選択肢
耐震等級に加えて、建物の揺れを制御する技術も進化しています。
- 制震構造: 建物内にダンパーなどの装置を設置し、地震の揺れのエネルギーを吸収して建物の変形を抑えます。繰り返しの揺れに強く、建物の損傷を軽減する効果があります。
- 免震構造: 基礎と建物の間に積層ゴムなどの装置を入れ、地面の揺れを直接建物に伝えないようにする技術です。揺れ自体を大幅に低減できるため、建物内部の家具の転倒なども防ぎやすいですが、コストが高く、定期的なメンテナンスが必要です。
戸建て住宅では、コストと性能のバランスから「高耐震(等級3)+制震」の組み合わせが現実的な選択肢として人気を集めています。
地震に強い建物の形状と構造
建物の形状や構造も耐震性に影響します。一般的に、「シンプルで、軽く、低い」建物ほど地震に強いとされています。
- 形状: 正方形や長方形など、凹凸の少ないシンプルな形状の家は、地震の力を均等に受け流しやすいため有利です。
- 重量: 建物が重いほど地震のエネルギーは大きくなります。構造別では木造が最も軽く、耐震性の面で有利になる場合があります。
- 高さ: 2階建てより平屋の方が、建物の重心が低く安定しているため、揺れの影響を受けにくくなります。
5. 「在宅避難」を想定した住宅設備を整える
災害が発生しても、自宅が倒壊や浸水の被害を免れていれば、避難所ではなく自宅で生活を続ける「在宅避難」が基本となります。ライフラインが寸断された状況でも、安全で快適な生活を維持するための設備を備えておくことが重要です。
ライフラインの確保(電気・水)
災害時、電気・水道・ガスといったライフラインは停止する可能性が高いです。東日本大震災では、水道の完全復旧に3週間以上かかった地域もありました。
- 電気: 太陽光発電システムと蓄電池を導入すれば、停電時でも日中に発電した電気を貯めて夜間に使用できます。スマートフォンでの情報収集や照明の確保に役立ちます。ポータブル電源も手軽な備えとして有効です。
- 水: エコキュートや貯水タンクを設置しておけば、断水時にタンク内の水を生活用水として利用できます。また、雨水を貯めておく雨水タンクも、庭の水やりやトイレ用水として活用できます。
非常食や防災グッズの備蓄
ライフラインの備えと同時に、物資の備蓄も欠かせません。最低でも3日分、できれば7日分の食料、飲料水、携帯トイレ、衛生用品などを準備しておきましょう。備蓄品は、すぐに取り出せる場所にまとめて保管しておくことが大切です。
6. 避難経路と避難所の安全性を確認する
自宅が危険な状況になった場合に備え、最寄りの指定避難所までのルートを確認しておくことは命を守る行動です。重要なのは、単に場所を知るだけでなく、実際に歩いてみることです。
ハザードマップと照らし合わせながら、「この道は浸水する可能性がある」「このブロック塀は地震で倒れるかもしれない」といった危険箇所をチェックしましょう。特に小さなお子さんや高齢のご家族がいる場合は、安全で移動しやすいルートを複数検討しておくことが望ましいです。
また、津波浸水想定区域内では、津波避難タワーや津波避難ビルといった緊急避難場所も指定されています。これらの場所も事前に確認し、いざという時に迷わず行動できるように備えましょう。
7. 中古物件は「維持管理状態」をチェックする
新築物件と異なり、中古物件は経年による劣化が避けられません。どんなに耐震性の高い設計でも、維持管理が不十分では本来の性能を発揮できません。内見の際には、以下の点を注意深くチェックしましょう。
- 外壁のひび割れ: 幅0.5mm以上のひび割れ(構造クラック)は、雨水が浸入して内部の鉄筋を錆びさせ、建物の強度を低下させる原因になります。
- 基礎部分の亀裂: 建物を支える最も重要な部分です。大きな亀裂やコンクリートの剥離がないか確認しましょう。
- 雨漏りの跡: 天井や壁にシミがないかチェックします。雨漏りは建物の構造材を腐食させる可能性があります。
専門家によるホームインスペクション(住宅診断)を利用して、目に見えない部分の劣化状況を確認することも、安心して購入するための有効な手段です。
8. 保険と行政の支援制度を最大限に活用する
物理的な備えと並行して、経済的な備えも重要です。万が一被災した際の生活再建を支えるために、保険や公的支援制度について正しく理解しておきましょう。
災害に備える保険の知識
住宅に関する損害保険には主に「火災保険」と「地震保険」があります。この二つの違いを理解することが重要です。
- 火災保険: 火災のほか、台風による風災や、洪水などの水災による損害を補償します。しかし、地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする損害は補償の対象外です。
- 地震保険: 地震・噴火・津波による損害を補償する唯一の保険です。火災保険に付帯して契約する必要があり、単独では加入できません。保険金額は火災保険の30%~50%の範囲(建物5,000万円、家財1,000万円が上限)で設定されます。
津波による被害は地震保険でしかカバーされません。沿岸部に住む場合はもちろん、静岡市で家を持つなら地震保険への加入は必須の備えと言えるでしょう。
静岡市の耐震対策支援制度
静岡市では、市民の住宅の耐震化を促進するために、様々な補助制度を設けています。特に古い木造住宅にお住まいの方は、これらの制度の活用を積極的に検討しましょう。
- わが家の専門家診断事業: 1981年5月31日以前に建てられた木造住宅を対象に、市が専門家を派遣し、無料で簡易な耐震診断を実施してくれます。
- 木造住宅耐震事業: 耐震補強工事にかかる費用の一部を補助する制度です。設計費と工事費が対象となります。
これらの制度を利用することで、費用負担を抑えながら自宅の安全性を高めることが可能です。詳細は市の建築安全推進課などに問い合わせてみましょう。
まとめ:自助と共助で築く、災害に強い暮らし
静岡市で災害に強い住まいを選ぶための8つのポイントを解説しました。
- リスクの理解: 地震・津波、洪水、土砂災害のリスクを把握する。
- ハザードマップの確認: 土地の安全性を客観的なデータで確認する。
- 地盤の評価: 固く揺れにくい地盤を選ぶ。
- 建物の強度: 「耐震等級3」を目安に、構造的に強い家を選ぶ。
- 在宅避難の備え: ライフラインが途絶えても生活できる設備と備蓄を。
- 避難経路の確認: 安全な避難ルートを実際に歩いて確認する。
- 維持管理状態のチェック: 中古物件は劣化状況を慎重に見極める。
- 保険と支援制度の活用: 経済的な備えも万全にする。
完璧に安全な場所というものは存在しません。しかし、リスクを正しく理解し、一つひとつの対策を積み重ねることで、被害を最小限に抑え、大切な家族と財産を守ることは可能です。本記事で紹介したポイントを参考に、あなたとご家族にとって最も安全な住まい選びを実現してください。
合同会社KUREBAは、静岡県を拠点に活動するWebの専門家集団です。
効果的なWebマーケティング戦略や、ユーザーに響くホームページ制作でお客様のビジネスをサポートします。
ご興味のある方は、ぜひお問い合わせフォームからお気軽にご相談ください。
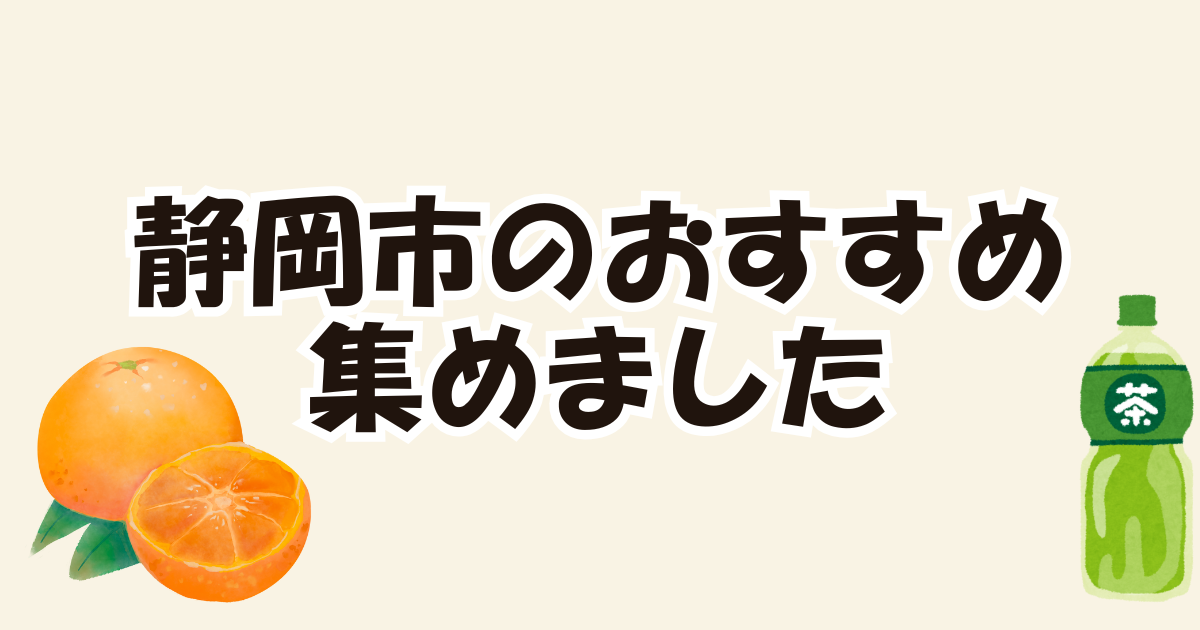
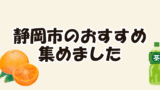
コメント